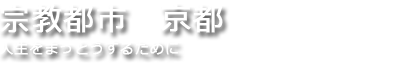第3回 医療と宗教を考える研究会 公開シンポジウム/メッセージの詳細ページ
第3回 医療と宗教を考える研究会 公開シンポジウム
~京都発・知足の哲学~無縁社会と終末期医療を考える
日 時 : 2011年2月13日(火) 13時~17時
会 場 : 相国寺承天閣美術館2階会議室
長谷川
本日はお集まりいただきありがとうございます。 団塊の世代が第一線を退きはじめ、また、その親たちが、そろそろ看取りの段階を迎えつつあります。 そんな中で、終末期の問題は、日本国民の多くの方々が、自らの問題として、課題として考えていくときを迎えたのではないかと思っております。 今、日本では、自宅で最期を迎えることが少なくなり、病院で看取りをお願いすることが多くなっています。
そのようなときに、医者と本人、あるいは医者と家族とは、どんな関係を持てばいいのか。 また、医者と本人や家族をつなぐ、仲介役を誰かがつとめることができないかということが、この研究会の発端でありました。 去年の夏以来、研究会を重ねて参りましたが、一度公開シンポジウムを開き、市民の皆様のお考えを聞いていてみようということで、今日の日を迎えた訳です。
今日は、それぞれの方のレジュメ、資料以外にも、医療関係者、宗教関係者、各種団体の方々に対し、アンケートを行わせて頂きましたが、その資料をお配りさせて頂いております。 せっかく京都でやるわけですから、終末期を豊かに過ごすには何が必要なのか、どのような生き方が求められるかにまで踏み込みたい考えております。
では、この研究会の座長を務めて頂いております、国立社会保障・人口問題研究所所長の西村周三さんから趣旨説明を頂きます。 よろしくお願いします。
■趣旨説明

西村周三氏 (国立社会保障・人口問題研究所所長)
西村でございます。 よろしくお願いします。 まず、これまでの経過を、具体的に少しご紹介しておきたいと思います。 この京都で宗教のあり方を考える必要があるのではないかという話を、後ほど対談に出て頂く堀場雅夫さんとお話をしておりました。
かつて京都市は、仏教会との間で不幸な時代がありましたが、私はそういうことはあまり知りません。 これからは心の問題が大事と思うこの社会において、仏教会に活躍していただきたい。 特に経済界が困っている。 そして、医療の問題も医療界だけでは解決できない問題をたくさん抱えている。 そんなことで、仏教会の方ともお話をさせて頂き、このような会を持ったわけです。 今日は終末期医療というテーマで、このような話をするわけですが、もう少し広く言えば、終末期医療だけではなくて、医療と宗教をいろんな意味で広く考えていく。 そして、その背後には、こういったことの研究会のアドバイスを頂いた中野東禅さんから、今の日本の経済のあり方についても、考え直す必要があるのではないかというご指摘を頂きました。
私ども、経済をやっている者と致しましては、これは当然一緒に考えていく必要があると思った次第でございます。 皆さん、恐らくご承知であると思いますが、高齢者の問題が大変難しい問題を抱えはじめています。 それだけではなく、無縁社会、朝日新聞によると「孤族」という表現をしていますが、それらが、ずいぶん表に出てきました。 若い方にも、雇用、仕事がないということが、一番の問題として捉えられております。 こんなふうに、若い方にも、いろんな社会の歪みが生まれてきている。 雇用問題は、当然、経済問題であると同時に、心の問題と療法が絡んでいるという。 そういうことを含めて、タイミングとしては、医療界、仏教会、そしてもちろん、キリスト教の方々、そして、経済界の方々、いろんな人間が集まって、いろんな問題を考えていこう。 そして、京都は非常に豊かな人材を抱えた地域でございますから、いろんな意味でこれらを進める「場所」としてもいいのではないかということで、こういう会を持たせて頂いている訳です。
それぞれのご専門を究められた方々がお集まりになっておられますので、まとめていくのは大変だと思っております。 是非ともみなさんの協力をお願いしたいと思います。 よろしくお願いします。 ではつづいて、これまでの経過についてお話し致します。 この会は、昨年8月に、東京大学名誉教授であり、医師でもあり、生物学、倫理学等に造詣が深い大井玄先生、そして、経済界という立場から、終末医療のホスピス、緩和病棟をお持ちで、京都経済同友会の代表幹事もされている田辺親男さんのお二人に問題提起をしていただきました。
次いで、12月には、日本バプテスト連盟医療団理事長の山岡義生先生、全仏教会事務局長の戸松義晴さんにお話をうかがいました。
そして今日は、洛和会音羽病院院長の松村理司先生に、また、いろんな議論をする中で、法律の問題が関わっているという認識がございますが、最近、厚労省で「終末医療のあり方に対する懇談会」というのがはじまり、その委員会メンバーとしてご活躍されている、東京大学公共政策大学院と法学政治学研究科の教授でもあられます、樋口範雄先生にお話を伺おうと思います。 また、僧侶であって医師である、「僧医」の対本宗訓先生、そして、京都仏教会の理事で圓通寺のご住職であります、北園文英さんにもお話を伺います。 さて、今日初めてお見えの方もおられますので、少しだけ、従来、私が申し上げた事についてお伝えしておこうと思います。 その前に申しておきたいのですが、私、昨年から公務員になりましたが、今日お話しすることは、私一個人の意見であります。
実は、これから申し上げる問題は、どちらかというと宗教家が表に出られるような話ではないという問題として、展開してきました。 つまり、医師と市民との間での問題として、議論が進んでまいりました。 実は私は、その背後には、西洋の個人主義が根強く入っていたとおもっております。 どちらかというと、医療が民主化する流れが始まったのは、欧米から入ってきたのです。 たとえば、「インフォームドコンセント」という概念があります。 日本は欧米と比べて明らかに遅れて、癌の患者さんに対して告知をするということが進みました。 その間、失礼な言い方をすると、社会学者等が、欧米の発想で、「医者が全く説明しないのはけしからん」と、「私たちの生命を医者が独断で決めているのか」という発想もありました。 そういう発想のもとで、欧米がずいぶん意識を変える努力をしてきたということは、十分にあるわけです。 ところが、これが、日本に入ってきたら、かえって日本のような風土には、人が人を思いやる、個人主義ではない(この表現は微妙で、思いやることがないことを「個人主義ではない」と言わず「利己主義」と言いますが)利己主義が一緒になって入ってきた。 そこで、欧米の思想が、日本の風土と関係なしに入ってきました。 一番の表現は、「自己決定権という表現です。 これは、ある意味当たり前で、「自分の命は自分が決定する権利を持っている」ということです。 そこまでは正しいのですが、私たち日本人には、「私の命は私のものではなくて、私の妻や息子の命でもある。 あるいは、ご先祖様から頂いた命でもある。 そういう、いろんな命をもっているという認識は、あまり西洋から入ってきた医療の考え方ではありませんでした。 「自己決定権」とは欧米とは違うものになっていると思います。
しかし、お医者さんの立場を考えると、そんな簡単ではない。 いろんな説明を専門用語でやる必要があって、それを説明しなければならない。 そして、とても大事なポイントは、前からずっと付きあっている人じゃない、初めて合うお医者さんと向きあって、ちゃんと理解出来るかということ。 実はこの会の催しに関して、宗教者が医療現場に関わることができるかというアンケート結果がありまして、実は、医療者は、とても大きな期待をしている。 そして宗教者もなんとかできると思っている。 ところが、一般市民はそうではない。 最近では、お医者さんと一般市民と、その間に、たとえば移植であれば、「移植コーディネーター」とか、コーディネーターがやってくれるほうがいいのではないかというのが、一般的ではないかと感じています。
私たちは、死という問題に関しては、普通の専門家で物事が事足りるとは思っていない。 やはり、非常に重大なのは、心と思っている。 だから、私は宗教者に期待したい。 お医者さんに対しても主治医としている方は信用できるが、そうでない方は信用できるわけではない。 おそらくそれは、宗教者、お坊さんとの関係もそうで、お坊さんとの関係も日常的に希薄になっている。
お葬式の時だけお願いしますということになっている。
もう一つ、家族の問題。 日本では企業社会といわれ、企業が何でも、たとえばお葬式までも面倒みる時代がありました。 そして、地域社会です。 しかし、今40歳の人が結婚しないで子供もつくらないと、家族がいなくなります。 その兆しがすでに出ております。 「家族」「地域社会」「企業」これらとの関係を、これからどう考えていくかが大事で、特に、終末医療に関しては、家族との関係をどう考えるかも大切です。 日本社会は、本人も家族も、お互い相手のことを思いやりすぎて、優しすぎて、かえってうまくできていないのか、というのが私の考えです。 昨日もテレビでやっていましたが、40歳ぐらいの方が、親の介護のために会社を辞めて職を失い、親が亡くなった後、路頭に迷うことが起きています。 もちろん政府、企業の責任と、いろんなことが言えますが、同時に親子の関係をどう考えていくかも、新たな問題として出てきていると思います。 そういうわけで、「家族」という問題を考えたいのです。 そして、もう一つは、医療機関との問題です。
こんなふうに、わからないことがたくさんある時、どうやって決断していくかが問題となってくる。 そんな時、お坊さんは、日頃はいりませんと思っていても、普段からちゃんと付きあっていくと、なにか良いことを言ってくれるのではないかと思う事があります。 実際に、今回この会を通じて、いろんな僧侶の方とお会いし、この人とつきあっておいてよかったと思うことが多いです。
そういうことを含めて、これから 4つのステージごとの整理をしたいと思います。 その4つは、「親を看るとき」、「どこで死ぬかを決めるとき」「自分の終末」、「家族が亡くなった後のグリーフケア」です。 これらをステージごとに整理して話をするのがいいのではないかと。
私は申したように、今の社会が非常に大きい変化を遂げていることも視野に置きながら、終末医療の話を伺いたい。 私は素人ですが、人間関係だけで生きているので、お医者さんも、市民の方も、お坊さんも、今回を通じてたくさんお知り合いが出来ました。 そういうネットワークづくりであれば、私にご相談頂ければと思います。
では、このあと4時半まで、皆さんのお話を伺いまして、その後、ご意見を伺おうと思います。 よろしくお願いします。
長谷川
どうもありがとうございました。
次に、シンポジウムにうつらせて頂きます。 生老病死、家族のあり方と終末期医療ということをテーマに、4人のパネリストの方々にお話を伺います。
西村
では、紹介頂いた方々のお話をいただき、その後、意見交換をしていきたいと思います。 ではまず、最初に松村さんにお話頂きます。
■シンポジウム「生老病死~家族のあり方と終末期医療」

松村理司氏 (洛和会音羽病院院長)
松村でございます。 私が今日話す内容は、西村先生ではありませんが、現在勤めている音羽病院とは関係ありません。 この立派な会で、なぜ、私が話しているのかもわかりません。 皆さんのお手元に資料が渡っていると思いますが、これにそってお話したいとおもいます。
私は前任地の舞鶴市民病院というところで、約20年にわたり勤務していたわけですが、小さな病院でしたので、日本人の優れたお医者さんが長期に来てもらえる訳ではなかったので、アメリカでは当時、十数年勤めると、半年間休める制度がございましたので、それを利用して、立派とされる医者に来てもらいました。 その方々は、当時の私よりも年代が上でしたが、50~70歳ぐらいでしたか、その一般内科医にきてもらい、若い研修医を教えてほしい、医学的な力を、より効率よく身につけてほしいと思ってはじめたプログラムがありました。 これは20年ほど続きまして、それをまとめたのが、この「大リーガー医に学ぶ」という本です。 その中で、約10数年前になりますが、「20世紀の日本の医療」という、たいそうなことを言っていますが、当時の日本の医療を振り返って、その時に思ったことを、数枚のスライドで見て頂こうと思います。
こちらは、京都の医大で、当時45歳ぐらいであった私と当時55歳ぐらいであったアメリカ人医師が、そこに行って、研修医から質問された内容です。 70歳を超える患者さんで、膵臓癌の手術を一度、放射線療法を二度されている。 経過は良かったが、一年経って全身倦怠、体重減少を来たすようになる。 入院後早速IVH(水分で栄養をとろうとする治療)をはじめましたが、この2ヶ月で、10キロの痩せが続いている。 どうしてか?どうしたらよいか?ということでした。 研修医は一生懸命カロリー計算をしているということでした。
その場には、若い研修医が15名ぐらい来ておりました。 それに対し、Bob Pieroni先生(老人医療の専門家ですが)は、「それは、末期だからだろう」という回答だったのです。 末期というのは、人間はそういうものなので、医療が出る幕ではないという回答でした。 また、それに対して、指導医はどのように考えているか。 また患者さんは自分の事態をどのように考えられているかと聞かれました。 すると指導医の思惑は特にないとか、他の科にいた時の以前のカルテが見あたらないので、はっきりしないとか。 病名は一応、慢性膵炎と思われているが、それについて患者さんと話し合ったことはないということでした。
後に、Pieroni先生は、間に入っていた私に言うんです。 「アメリカでは、この状態でIVHのカロリー計算はしないよ」と。 「アメリカなら、こういった末期患者の場合は、研修医でも、出来るだけベッドサイドにいるようにと指導すると。 なぜなら、老人は予備力が乏しいから、治療行為がはたして貢献になるのか、それとも害を及ぼすことになるのか、その判断がむずかしい。 アメリカの老年医学会では(20年ほど前の話ですが)、演題の約2割は倫理的課題ですよと言っておりました。
第2の例は、こちらも約20年前の、ごく一般の民間病院での、研修医の質問なのですが、「85歳の女性で、糖尿病と高血圧で30年来、治療中の方。 39.5℃の発熱、悪寒、咳があり、レントゲンをとると、肺が真っ白になっている状態だった。 酸素の状態も枯渇していて、心臓の超音波で弁膜症を認める。 」しかしこれは、すこし専門的なことになるのですが、年齢がいくと、これは普通に見られる現象で、それだけでは心臓の病気とは言えないです。 「様々な治療をしたけれども悪くなって、腎不全も合併するようになり、MRSAという病原菌が、あちこちからでてくるようになった。 熱は続き、肺はもっとひどくなって、入院してから3週間で人工呼吸、一週間後は、腎透析を開始して、入院後40日目に、肺に管をいれて、いろいろしているけれども5日前からは、深昏睡が続いている」と。 ICUにも3週間はいっているが主治医以下、必死の様子で「出来ることはしてきました。 今後、医学的にどうすればいいでしょうか?」「彼女には、何がいるのでしょうか?」ということなのです
それに対し、感染症専門医のMarty Raff先生は、「She needs a prayer.(彼女はただ祈るのみです)」と答えました。 わたしも「えっ?」と聞いたのです。 医学的な場での回答だったものですから。 「これは、なにもできない状態だ。 安らかな死があるだけです。 病や死のあり方は、文化や風土の影響を受けるので、日本のことはよくわかりませんが、アメリカではこの状態でさらに治療に情熱と時間をかけることはありません。 自分なら、人工呼吸器は外すでしょう」と。 そもそも、この患者さんは助かる見込みがなかったのではないかと。 英語で彼が言ったのは、「You were fighting the losing battle.(負けいくさをどう収めるかだったのですよ)」と。 ただ、感染症の専門家ですので、医学的な事で言えば、抗生物質の使用前に、血液培養を何回、どのようにしたかとか、そういうことは、付け足しのような格好で聞いておられました。 この2例が、約20年前の当時のエピソードということで、末期の患者さんのもとで、そのときに、いろいろ感じさせられたことの代表的な例であります。 そういうなかで、当時思ったのが、「和魂洋才」。 亡くなりつつある患者さんの魂、精神、こころが、非常に縮かんで聞こえてこない。 どうもバランスを欠いているのではないかと思いました。 そういうことを20年ほどやって参りますと、西村先生もおっしゃっているように、医療の現場という中でも、日米の差、メンタリティの差を感じさせられるのです。
アメリカ人から漂ってくるのは、個人主義と自己決定権なんですね。 個人主義と自己決定権は、勝手な言い方かもしれませんが、特にアングロサクソンの方々にとって、侵されるのは許すことが出来ないというものなんです。 しかし、日本は個人である前に、集団志向性社会ゆえの関係を非常に大切にしていて、個は非常に曖昧であることを感じました。
前回のこの会でも、ひょっとしたら過剰なのかもしれない胃瘻造設のことが問題になっていたと思うんですね。 その胃瘻造設にまつわる家族親族の躊躇などはものすごくあるわけで、これを決定するのは誰であるかとなってくると、欧米のように、患者さん個人の決定には、なかなかならないところがあります。 たとえば、認知症になられても、「元気な時に、うちのおばあちゃんは、しないと言っていた」といって「ああそう」とは終わらないことがある。
そこで、私の好きな評論家に小浜逸郎という方が「癒しとしての死の哲学」というのを書かれていて、今日申し上げたいことをうまく代論して頂いている感じがしますので、少し読んでみます。
「日本人は、要するに、『相手を気にする』ということで『自分を立たしめる』民族なのである。 格別『相手の立場を慮ってあげる』思いやりのある優しい民族なのではない。 また、特に『真実と対面することから逃避しようとする』臆病な民族なのでもない。 相手と自分との関係に配慮する事を通じて初めて、自分を実現させようとする民族なのである。 したがって、親しい者の癌について告知することをためらうという心情には、関係性の維持というところに自己存立の根拠をおいている日本人特有の実存構造が映し出されていると言えるだろう。 これは、いいことでもわるいことでもなく、ただそのようにしかありえないということにすぎない。 そして、この構造はなかなかに変わりそうもないだろう。 」というふうに、彼は言っています。
そういう中で、最後のスライド、「21世紀の(終末期)医療の自覚」を見て頂くのですが、今後の、特に終末期医療なんかを考えますと、やはり、押さえておくべき点はあるだろうと思うのです。 西村先生からも「無縁社会」という言葉がでましたが、超高齢社会において一人でおられる方、あるいは、20代からでも、無縁の社会が今あるわけです。 先ほどから大事と言っている「関係」が希薄化してきている。 これに対してどうするのか。 一つは、身の回りの自立だけでない自立を自覚する契機であろうと思います。 つまり、人間はどこまでいっても自己責任がどうしてもいるので、それはやっぱり、考えないといけない。 もう一つは、もっと現実的な話になりますか、最近「health literacy/medical literacy」という言葉を使います。 これは、現在、インターネットなどの普及で、膨大な情報量があるわけで、これらを上手に利用できる能力を個人が磨いておかなければと思う次第です。
次には、研修医を指導する者として、もっと上にいる指導、ここでは「人生経験に富む医療者」と書きましたが、半歩出て、胃瘻造設とか、人工呼吸を外すなどという大事なところは、自らならどうするかという死生観を言う。 一歩二歩なら出過ぎかもしれないのですが、半歩出て、自らの死生観を伝える。 自分ならこうするし、自分の親ならこうするという死生観を漏らさないと、家族が決定出来ないし、経験したことのないことの連続で、決定した家族の罪悪感が出てくる。 それをこういう形で回避できないか。 そこに、私は、宗教家の出番の一つがあるだろうと思うのです。
もう一つは、今日の主旨からはずれるかもしれませんが、臓器別の専門医が非常に華々しい日本の医療の中で、それと全般にジェネラリスト(総合医)と言われる人をもっとたくさん養成することが必要だと考えています。 終末期医療は、臓器別専門家だけの足し算では解決出来ないと思っています。 医療資源が爆発的に要るので、中福祉を求めるなら中負担もいるぞという覚悟いる。 日本の医療はうまくいっているといわれますが、近接性、すぐに医療にかかれるということと、費用と、医療の質と、この3つですが、だいたいこの中の2つしか実現できないと言われています。 この3つともに、うまく展開できるかどうか、これはよほどうまく考えないと難しいだろうと思っています。 医師の側からの反省としては、このように考えているわけです。 今日の課題で申しますと、患者さんの老死に関わったときの医師の出方としては、やはり経験に富む人が、半歩出て、死生観を漏らすということが大切です。 そして、これは宗教者の出番の一つでないかとおもいます。 これを一つの問題提起とさせていただきます。 ありがとうございます。
西村
どうもありがとうございました。 質問もあるかとおもいますが、4人の方々にお話をお伺いしてから、ご質問を受け付けたいと思います。 それでは、次に法律のご専門でいらっしゃいます、東京大学の樋口先生にお話をお伺いしたいとおもいます。
樋口範雄氏 (東京大学公共政策大学院教授・東京大学大学院法学政治学研究科教授)

ただいまご紹介に預かりました、樋口と申します。 私は、法科大学院と法学部でいくつかの授業をもっています。 法科大学院では生命倫理と法に関する授業をもっていまして、先週も約60人のこれから弁護士になろうとする人たちの試験の問題を採点していました。 そして、終末期医療に関して、私が何を言えるかということなのですが、ここ5~6年ぐらい、私が考えた事などをお話ししたいと思います。
お手元に資料が配られているかとおもいます。 「終末期医療と法~なにが問われているか~」と題名をつけましたが、今日は、駆け足で要点を申しあげたいと思います。
要点は次のようなことです。 問われているのは終末期医療のあり方ですが、同時に、わが国における法のあり方も問われているのではないかということです。 法が人々の、このケースでいえば終末期医療の対象である患者家族の役に立っていないのではないか。 今日は、仏教の関係者の方が多いとしたら、私の意識でも、「お寺の人に頼むのは、死んでから」というのがあります。 死ぬまでは、率直に言うとお寺さんも役に立たない。 死んでから急にでてくる。 ただ、お寺さんより法律が悪いのは、出てきたら、殺人罪じゃないかといって出てくるという印象があるので、たちが悪い。 それはやっぱり、死ぬ前から役にたつような、そういうあり方を考えるべきなのではないかと。 最近そう思うのです。 そのお話をさせて頂こうと思います。
医療関係で裁判になると、教材となって、大学で使われることになります。 そこで、医事法判例百選という書物に掲載するので紹介したらと、頼まれた事件がありました。 2002年の最高裁判決なんですが、癌告知の判決です。 ではどんな事件かご紹介します。
秋田の病院に老人がずっとかかっていました。 「胸が痛い」ということでした。 ある時、はっきりわかりました。 肺がんの末期でした。 でも、お医者さんは、本人には「肺がんの末期だよ」と言えなかったのです。 そのうち、そのお医者さんが病院を転勤することになった。 カルテには、「まだ告知はしていない」と書いて、次の医者に引き継いだのですが、受け継ぎが悪かったのか、次の医者も話さないままだった。 で、ある時、その老人が倒れました。 救急車で運ばれて、秋田大学病院に運ばれました。 すると、その秋田大学病院の先生はすぐに、本人にではないですが、家族に「肺がんの末期です」と告げたのです。 そこで家族はびっくりするわけです。 悪かったのは知っていたが、癌の末期だったのかと。 そのまま入院し、亡くなってしましました。 そして、前の病院を訴えたのが、この事件です。
それだったら、もう少し早く教えてくれたら、もう少し優しくしてあげられたかもしれないという気持ちが遺族に残ったわけです。 気持ちはわかりますよね。 このように、癌告知で最高裁まで争ったのは、これで2件目です。 で、前の1995年に、名古屋の日赤で同じような事件があったのですが、そのときは、全部、病院の勝ちでした。 しかし今回、最高裁は、患者の遺族側を勝たせた。 はじめてです。 これは、注目されました。 最高裁はなんて言ったかというと、「当該医師は、診療契約に付随する義務として、少なくとも、患者の家族等のうち、連絡が容易な者に対しては接触し、同人または同人を介して、さらに接触できた家族等に対する告知の適否を検討し、告知が適当であると判断できたときには、その診断結果等を説明すべき義務を負うものといわなければならない」ということです。 簡単に言うと、家族には知らせてあげてもいいのではないかと。 それをやってないので、これは、慰謝料を認めてくれた事件なのです。
この判決を、紹介しろと言われたわけですが、私より前に、いろんな法律学者がいろんな雑誌に十数本取り上げて紹介してある。 どういうところに焦点が定まっていたかというと、この判決では「本人にどうしても知らせなければいけない。 」とか、「自己決定権だから。 」とは言っていない。 「家族には知らせないといけない」という話で本当にいいのだろうかというのが一点。 二点目は、「すぐに家族には知らせなさいよ」とは言ってない。 ちゃんと読めば、「適否を検討し、告知が適当であると判断出来た時は」と言っている。 じゃあ何をやれば、家族に対して誠実に配慮したことになるのか。 いったいこれは、どういう意味なのか。 このような点を中心にさまざまな判例評論が出ているのです。 私はこれらをいろいろ考えて読んでいて、突然、本当はもっと重要なことがあるのではないかと思うようになりました。 なにしろ、医者が末期癌だということを、患者または家族にどう告げるか、あるいは告げるべきか否かということだけを、みんな論じている。 そんなことだけが本当に重要なのだろうか。 もちろん重要だが、本当に重要なのは、告げた後、どうなるかということではないか。
しかし、法律は、あるいは法律家の関心は、告げたらもうおしまいなのです。 そんな法律はいるでしょうか。 少なくとも、この、亡くなったご老人にはいらないでしょう。 大事なのは、実際に告知した後、どういうケアが続いていくんだろうとか、お医者さんもはっきりとした余命はわからないと言うけれども、一応予測をつけてみて、それをどう過ごすか。 また、家族はどういうことをしてあげられるかということです。 そういうことが、大事なのであって、それを「点と線」という話にしたのです。
法律家は、点の議論だけやっているのです。 それは、ほんとうに一生かけてやることだろうか。 もっと大事なことがあるのではないか。 この判決文を読むと、終末期を迎えた人に、さっき言った事情でうまく伝えられなかったということは、わかるんですが、末期癌だったということがわかった時に、どういう治療がでてきるかと医療側で話しあったことは、一切でてこないのです。 そういうことに、弁護士も裁判官も興味がないからなのです。 本当は、そっちが大事なのではないかという気がするのです。 法律のあり方は問題だなあと思ったのです。
終末期医療の懇談会というのが、厚労省のほうでも、ついこの間まで行われていたのですが、中川翼さんという、札幌で終末期の方をたくさん抱えておられる病院の先生で、非常に立派な先生なのですが、その方が、もっと法律の専門の方にがんばってほしいと、もっと法的な点をはっきりさせてほしいと言われるのです。 どのようなことを言っているかというと、たとえば、人工呼吸器を取り外したとしても、こういう場合だったらいいんですよと、はっきり法律に書いてくれということなんです。 この場合の法というのは、刑法、殺人罪です。 こういうのが出てくるので、困っている。 何とかしてくれと言うことなんです。 気持ちはわからなくはない。 そういう話はたくさんあります。
ここで、アメリカの話をしてみたいと思います。 アメリカの「生命倫理と法」というケースブック(casebook)、これは、アメリカの法科大学院の教材なんですが、その1ページ目に、いきなりこういう設例がでてきます。 仮の設例ですが、有りそうな話です。 「ある金曜の午後4時半、300ベッドの病院の顧問弁護士であるあなたのもとに、電話が入った。 電話をかけてきたのはスミス医師。 弁護士はこの医師と友人関係でもある。 37歳の余命約1ヶ月の末期の肺がんの患者を診ているが、患者はもう、化学療法もペースメーカーもやめてくれと言っている。 意識もしっかりし、何度も繰り返し言ってくる。 どうしたらいいだろうか?」という話です。
こういう時に、日本の法律家は何と答えると思いますか?「ペースメーカーを外してしまった場合は法律的に問題があるかもしれませんねえ。 」というようなことを言うのです。 そうすると、何も出来ないですね。 じゃあ、アメリカではどうなのだろうか?あれだけ多くの弁護士がいて、何かと裁判が行われる社会ですよね。 でも、casebookの次のページを読むと、弁護士は医者に対し、「倫理委員会に相談したらいいですよ。 」と言うとあるのです。 弁護士がそう言うんですよ。 そのあと、倫理委員会では「もう外してもいいでしょう」という話になり、法律家としてはそれが最善であるということになるのです。 お医者さんにとって、いい弁護士さんが友達にいて幸運でしたねとも書いてあります。 こういう話が、弁護士を養成するロースクールで使う本の最初のページに出ているんですね。 「殺人罪になるかもしれませんよ」なんていう、くだらないことは、誰も言わないわけです。 どうして日本でだけそういう話になるのだろうということなんです。
次に、これはアメリカの医師国家試験問題の模擬試験問題ですが、ここにも、これと同じような問題が出ているのです。 国家試験の問題というのは○×問題ですので、必ず正解があります。 これら国家試験の問題の中で、私が関心を持つのは、医療倫理という問題です。 倫理って、そう簡単に正解が見つからないものですが、正解が見つかる範囲で試験問題を出しています。 いくつかご紹介しましょう。 「男性が事故に遭い、人工呼吸器を装着されてICUに運び込まれたが、あらゆる基準で脳死状態にあると判定された。 (アメリカは脳死が死ですから、これはだめと言うことです。 )臓器移植カードを所持し、臓器提供の意思を示していた。 臓器移植チームが家族に連絡を取ったところ、臓器提供に反対するという。 どうすべきか?」
この問題の答えの4つの選択肢は、「A.人工呼吸器を止めて、臓器を摘出すべき」「B.心臓停止を待って、臓器摘出すべき」「C.裁判所の命令を得るべき」「D.家族の意思を尊重し臓器提供をやめるべき」となっている。 これは、アメリカの医者になる人の試験問題です。 では、アメリカの法律はどうなっているか?これは、自己決定権です。 本人が移植カードを所持しているからには、家族が反対しても、当然本人がいいと言えばいい。 アメリカの法律上はやってもいいということです。 どこの州でもそうなっています。
では、医療倫理はどうだろう?やはり法律通りになるはずだからAの「臓器摘出すべき」が正解か?・・というと、そうではない。 正解はDの「家族の意思を尊重し、臓器提供をやめるべき」なのです。
こうしないと、医者にはなれない。 法律通りにやれば医者としても正解だなんて話は、アメリカにはないわけです。 これを日本では誤解しています。 アメリカでは、法律上、脳死が死であって、本人の自己決定権だと言っていますが、法律だけで医療を説いてはいない。 法律家が上にいて、医者を指導しているなんてことは、あってはいけないのです。 やはり、医者はちゃんとしているということが大事なんです。 そういうふうに考えると、法と医療の関係ということが重要になってくる。
日本では、法学部で取り上げられる終末期の問題というのは、いわゆる「安楽死」「尊厳死」です。 資料にも京都・京北町の事例などがありますが、ほかにもたくさんあります。 しかし、このような事例を見ていきますと、人工呼吸器を取り外しただけで、起訴された事例はありません。 でも、弁護士がなんというかというと、「そういう可能性がある」とか、「疑いがある」とかと言って、脅すわけです。 脅しなのですよ。 今日の会のテーマは、「『知足』足るを知る」ですが、足るを知る人たちがそう言っていないのに、足るを知らない法律家がそういうことを言っている。 しかもその人たちは、その患者を見守ってきた人ではない。 最後の場面にだけ出てきて、くだらないことをいう。
そこで、厚労省ではガイドラインを作ったのですが、この内容は3点です。 人工呼吸器を外すときも、今まで日本で問題になった事例は、お医者さんが独断でやっていたケースです。 でもそれはいけない。 そこで、一人だけじゃやらないで下さいと決めました。 必ず、医療ケアチームで話し合った結果、仕方がないということにして下さいとしました。 そして2つめは、徹底した合意主義で、本人の意思を尊重し、しかも家族も合意をとって、その上で、仕方がない、「足るを知った」場合には呼吸器を外していいですよ、という話なのです。 こうなると、警察が出てくることはありえないと私は思うんですが、刑法上殺人罪にはならないとはガイドラインには書いてないから、だったらだめじゃないか?とも言うんですね。 3つめは、緩和ケアの重視・充実の必要性です。 本人にとっても、家族にとっても、痛いのは嫌だからです。 しかし、終末期になると、肉体が痛いだけではない。 心が痛んでいる。 死は必然的なものと認識はするが、笑ってられるわけではない。 緩和ケアには、精神的なスピリチュアルなものも必要となってくる。 これは法律家ではどうしようもないので、この3点について、なんらかの形で緩和ケアについて、予算をつけたらいいのではないかと言うことも出来る。
精神的なケアについては、心を扱うところの専門家が入ってあげることも、ありがたいことではないでしょうか? 我が国の場合、法律も問題だが、他の所でも足らないことがあって、それは単にお金の話だけではないという気がします。 生き方、死に方は、個人のレベルではあるが、法律に期待している人も多く、法を作れという要望もある。 これは、倫理が不明確だから、法ではっきりさせてほしいということなんです。 でもこれは危険です。
アメリカという社会は、多民族国家で、さまざまな人種がいる。 そういうところで、ある最低ラインを明確にしている。 医療倫理として、みんなが「そうだね」と言えるところを明確にし、その上に、場合によっては・・ということになる。 その基盤がないのに、日本で、法に頼るというのは、危ないのではないでしょうか。 いろんな手立てがありますが、法を使うときに、今、期待しているような人がつかう方法ではなく、もっと違った法の役立て方があるのではないかと考えている訳です。 どうもありがとうございました。
西村
ありがとうございました。 次に、ここに「僧医」と書かれていますが、僧侶であられて、医師でもある、対本宗訓さんです。 僧侶であり、かつ医師という立場から、お話を頂きたいと思います。 よろしくお願いします。

対本宗訓 (僧医)
ご紹介預かりました、対本です。 医学と法律の専門の先生からお話を伺うことができまして、私も常に、僧侶として、宗教者として、どうしていけばいいかと問い続けている立場から、非常によいお話を伺えてよかったと思っているところです。 今日は、私が今、メインに取り組んでいるところをお話しさせて頂こうとおもいます。
さて、お坊さんが、生老病死という様々な場に及んで、なぜ、医療の現場に入っていけないのか。 それはそもそも、考えているからいけないのです。 考える暇があったら行動するべきなのです。 そこをまず、なんとか皆さんにわかって頂きたいと思うのです。 やろうと思えば何だって出来る。 衣を着ている必要はない。 私は医療現場では衣は着ていられません。 そこで私は、「臨床僧」という言葉を考案いたしまして、一つの活動としてやっていこうとしているのです。
まず言えるのは、「何か一つ、資格をとりましょう」ということです。 お坊さんが入っていって法を説いても、誰も聞きません。 仏教の言葉を使わずに、自分の宗派宗門の言葉を一言も使わずに、患者さんに法を説ける人はおそらくいません。 それほどに難しいことなのです。 一般の多くのお坊さんが考えておられるような、「行けば何とかなる」ということは、全くの間違いです。 ですからまずは、スピリチュアルケアとか、心の説法は後回しです。 スピリチュアルケアとは何なのかも、わからないわけですから。 定義しようとする努力は大切ですが、その前に、生老病死の現実があるのです。 患者の痛みのほうが、先にあるのです。 だから、そこを間違えないことです。
そこで、生老病死の現場に入っていって、何ができるのか。 まず私は、手も汚さない、汗もかかない様なケアはないと、病院に勤務していて思います。 看護師だって、誰だって、汗をかいて手を汚して必死で患者さんのケアをしている。 そこにお坊さんが衣を着て入ってきて、スピリチュアルケアだなんてできない。 まずは、体を動かすことです。 そのためには、何か一つ、手がかりをもつこと。 ヘルパー2級でもいいし、ケアワーカーでもいいし、お坊さんの中には鍼灸の資格を持っている方もいる。 そのほかに、僕はリフレクソロジーをやりますという人も出てくるかもしれない。 また、カウンセラーでもいい。 なにかひとつ、手がかり、足場をもっていただいて、事前にトレーニングすることが必要です。
私は今、ロンドンの大学病院にいますが、たとえば、癌の治療では、いわゆる抗がん剤を使ったり、放射線医療とか、時には免疫療法とか、通常の治療と平行して、補完代替医療のチームが活動しております。 ほかの代替医療のチームには、針灸もあれば、リフレクソロジーもあれば、ヒーリングまであるのです。 それがしかも、NHS、日本でいう保険でカバーされる。 そして常に、一般のドクターとかナース、通常の医療のスタッフたちと打ち合わせながら、患者さんの求めに応じて、もちろん医学的な立場から、必要なものかどうかも、常に検討している。 そして何よりも患者さんからのフィードバックがあります。
実は、お坊さんというのは、あまり批判されない立場にあります。 かつて私はトップにおりましたので、批判されることなどありませんでした。 でも、医学部に行って立場が変わったのは、常に批判される、評価されることです。 医療現場では、患者、ナース、上の先生から、常に批判される。 でもそれは、悪口ではない。 そういうものがないと、なにも学べないし、自分も変わっていかない、成長しない。 そういうシステムが機能しているわけです。 しかも、補完代替医療のスタッフも、すべて保険に入っている。 これは、過失があったときの保険です。 また、法的とまではいきませんが、評価をします。 どこまでのものを身につけていて、どこまで再評価なされているか。 知識とかスキルをアップデートしているかどうか、それを評価する機関があり、必ずそれに入らなければならない。 そうしないと、患者さんも信用しないわけです。 何か起こったら大変なことになりますので。 それだけの専門性を要求されるのです。 それがイギリスの補完代替医療のチームのあり方なんです。
お医者さんたちは、普通考えると、科学者です。 心の病気を見るというのはというのは、もちろんありますが、魂や霊的な問題、たとえば死んだらどうなりますかということはないです。 でも亡くなる患者さんは、自分の死期がある程度解るというのです。 昔のお坊さんは、必ず7日前に死期を悟ったと言われますが、何かわかるんですね。 ケアしている方も、そういうことを念頭に置かないと、患者さんのサインをつい見逃してしまう。 何かおかしいといって、鎮静しようとするが、鎮静して楽になるのは患者さんではなくて、ケアしている方なのです。 やはり、そこで、何が起こっているかということは、もっときちっと見ていかなくてはならない。
私はそれを、周死期学としています。 これは周産期学の反対です。 周産期学は赤ちゃんが生まれてくるときの前後のプロセスですが、その反対という意味です。 わたしはそこに光を当てようということなのです。 赤ちゃんが生まれてくるときの分娩の仕組みは非常にうまくできている。 だったら、人間は亡くなるときも必ず、非常に安楽にそんなに苦しまずに次の世界に旅立てる仕組みが、魂の面でも備わっているはずだと、産婦人科をローテーションしたときに、直感したのです。 これはもう、宗教者としての目線が役に立ちました。
患者さんには、必ず、自分が亡くなるときには、意識的、無意識的に、旅立つ準備に入られます。 そのときがとても大切なのです。 我々の目には見えないのですが、自分より先に旅立った方がそばに迎えにきていらっしゃるようなそぶりの時もありますね。 聖衆来迎図という、阿弥陀様が雲に乗って亡くなる人を迎えにきたという図がありますが、阿弥陀様やイエス様でなくても、自分を心安らかにし、死の恐怖から放たれるなら、自分より少し先に旅立った人など、身近な人のほうがよほどいいのではないかとおもいますね。
さて、わたしたちお坊さんに欠けているのは、物を見る目です。 物質としての肉体を見る目は欠けています。 だけれども、一方でプロフェッショナルといえるのは、心や魂を豊かなものとしてきちんと見ていく目です。 これは必ずあります。 補完代替医療チームが共有しているものというのは、まさに、我々僧侶が基盤として持っているはずの心とか魂なのです。 では、それはお経の本のどこに書いてありますか?臨済録のどこに書いてありますか?たぶん書いてないです。 書いてある必要がないのです。 なぜなら我々は2千年前に綴られたお経を一字一句変わらず受け継いでいるのです。 しかるに、私たちの物の見方や社会や人間の心の表面的なあり方は常に変わっているのに、相変わらず千何百年も書かれた物のみに頼っている。 法律で言えば、なにかの条文があって、その解釈をすりあわせているように感じる事もあります。
だからといって、祖師方の言葉が、価値がない、もう色あせているとは全く思わないのです。 教えは、学ぶことがたくさんある珠玉の言葉です。 ただ、今日起こっている事を、常にカビの生えた文章とすりあわせないといけない訳ではない。 宗教は自分のためにあるわけです。 なにもお釈迦様のためにあるわけではないのです。 自分の目で見て、体で体験して、自分がどうすればいいのか答えをだす。 お手本の答えはどこにもありませんから、自分が選択したものが答えです。
そういうことを、私は自分の人生経験の中で学び取ってきて、今日に至っています。 私は補完代替医療の完のチームの人生観、死生観をだしましたけれども、これはお坊さんの、本来、寄って立つところであるはずなのです。 自分の目で見て、自分で、頭で考えることです。 そうすると自ずと、患者さんとの交わりの中で、自分の実際の人生の中で近しい人を看とった中で、自ずから死が見えてくるのではないかと思っています。
臨床僧の会は、何も規約で絞ろうとはしておりません。 資格を取って下さいというのは、ほんの足がかりにすぎません。 しかし、医療現場に入るためには、絶対資格は必要です。 なぜなら、現場で患者さんに接するとき、なんの予備知識もなしに接するということはできません。 たとえば、MRSAの患者さんがおられたときに、そこに素手で入っていけますか?わからない人は入っていくかもしれません。 あるいは、抗がん剤治療をやっている人の所に、スピリチュアルケアだといって、無造作に入っていけるか。 それはだめです。 抗がん剤を使いますと、免疫力が著しく低下していますから、感染を与えてしまうかもしれない。 それは命取りです。 そういうことも知らないで、入れるわけがない。 だから事前の教育は絶対必要です。
補完代替医療のチームでも、針治療の人だって、リフレクソロジーの人だって、みんな、介護学、生理学、病理学という基本的な単位を絶対とらなければいけない。 しかも何点以上のスコアで通らなければならないという、厳しい基準があるのです。 基本的なものをクリアしなければ、患者さんの前には立てませんよと言う厳しいものがあるんですね。 そこまでやって初めて彼らは患者さんの信頼を得て、ドクターやナースとも非常にいい関係で仕事ができるわけです。 こういうことが、なにかモデルとして学べるのではないでしょうか。 もちろん、国民性も違いますから、そのまま導入は出来ないと思います。 ただ、一つの学びとして、なにかヒントにはなるのではないかとおもっています。
私は、臨床僧の活動として、そんなにスムーズには進まないとは思いますが、いま名乗りを上げてくれている4~5人のメンバーと、まずは一歩を踏みだしたい。 一歩を踏み出すにはエネルギーがいりますが、2歩目はついていくと思っています。 まずは焦らずに、しかし謙虚にやっていきたいと思っています。
私の申し上げたいことは以上であります。 なにかご質問がありましたら、遠慮はいりません。 どんなことでもありがたく聞かせて頂きます。 よろしくお願いします。
西村
ありがとうございました。 短い時間で恐縮です。 続いては、この会の主催者の代表であり、円通寺のご住職の北園さんにお話をお伺いいたします。

北園文英 (京都仏教会理事 圓通寺住職)
前回参加させて頂きました時にも少しお話させて頂きましたが、30年ほど前に、京都は古都税の問題が巻き起こった時代がございます。 そんな時に、お坊さんの襟を正さなければということで、京都仏教青年会というのを立ち上げ、病院活動や福祉など、いろんな目新しいことを活動して参りました。 当時は大変な人数がいたしましたが、だんだん少なくなり、20名ほどになったのと、年も重ねて、もう青年ではないということで、バガボン京都と改名をいたしまして、病院を回ったりと、活動を続けております。
最初の頃は、病院に入りますと、お坊さんが衣を着て病院へ行くと、ああ、霊安室に行くのだなあと、また誰か亡くなったかなぁと、何回行ってもそういう感がありました。 病院のスタッフからも「今日は誰かお亡くなりになりましたか?」と聞かれたこともあります。 それがだんだん顔見知りになり、解け合う所も有りということで、患者とのコミュニケーションがよくなりました。
そしてまた、私の場合は、法話を致しませんが、老人ホームであるとか、知的障害者の所であるとか、ライトハウスのところとかは、法話的にずっと回って参りましたが、あまり効果はありません。 一方通行なのです。 難しいことをしゃべってもだめだし、また、悟ったようなことを言ってもだめです。 言っても向こうを向いている。 興味がないという、そういう感がありました。
私はそのなかで、書道という枠を持ち、実践的に動ける患者さんがいるならば、何かを書いてもらおうと、何か思い出の文字がないか、何か書けないか、ということからスタートしました。 ライトハウスの方も、何か書けるということによって、いろんな工夫をしてきました。 紙にも普通のものより、目の不自由な方にもわかりやすいようなものにするなどしてきました。 その時間内はたいへん楽しそうにしておられ、充実した時間が持てるとおっしゃっていました。
ただ、病院の場合は、健康な方ではないわけですから、なかなか難しいです。 がんばれよと言って帰るのもおかしいですし。 でも、「また来週来ますよ」と言うと、みんな期待を持って待っていてくれている。 20数年たちますと、私たちも来てあげているという気持ちがなくなり、今は、行かなかったら損するという気持ちがあります。 患者さんから教えてもらっているというか、患者さんの方が悟っているというか、行くと何かを得て帰ってくる。 しかし、帰ってくると非常に疲れ果てています。 なにか、吸い取られているのではないかと思うくらいです。
しかし、その時間は非常に楽しいです。 患者さんも、お医者さんに聞けない、看護師さんにも聞けない、家族にも言えない事を、私たちにぶつけてくる。 お坊さんは、なにかいい回答を出してくれるのではというものを求めてくる。 勉強になることもたくさんありますが、坊さんであってもわからんことはいくらでもある。 「坊さんなのにわからんのかね?」と言われたこともあります。 でも「わからんもんは、わからん」のです。 お坊さんもお医者さんも、それ以前に人間なのだから、わからんことはあるのだよと、次に来るまでに考えてくるからと。 それが延命につながるということもできますし。 その呼吸が、なかなか難しい。
そういうことにおいて、近年特に思うのは、お医者さんにはたいへん失礼かもしれませんが、コンピューター先生が多くなりました。 コンピューターばかり見て、患者の顔はみていません。 操作しながら、お話しされている。 患者さんは、何を聞いてくれたのかなぁと思い、次を求めて違うお医者さんの所へ行く。 でも、結局わからん、わからん、できている。 日本は問診が長ければ、それでお金がとれる病院はございませんし、アメリカのお話もされていましたが、アメリカも弁護士もTIME IS MONEY ですから、日本でも、そういうのがあれば、もう少し問診に時間が掛けられるだろうかとおもうのですが。 だから、私たちが行くと、そういう話が出てくるのかもしれません。
いかに、患者さんと向き合っていくかということでございますが、これが言葉は簡単ですが、実際は容易なものではありません。
私の寺は、公開したお寺でございますので、拝観者は少なからず来てくれますが、毎日、掃除したり、受付にいたりしていますが、だいたい60%ぐらいが同じ人です。 試しに来られている感じもします。 拝観しに来て、少しだけ見て、ずっとこちらに来てしゃべって、元気が出たから、もう帰ります、とか。 そういうことが、今の時代、必要なのではないかと。
中には、学校の先生で、体を悪くされて、精神的にも参っておられ、自宅待機になられている人がいます。 その方も、通っておられるのですが、自分でカンフル剤を得られたのか、だんだん目が変わってこられました。 そういうこともあります。 京都にはお寺が多くあり、お寺に参られると、どこにもお坊さんおられますが、お坊さんも忙しいので。 ただ、なにかそういう場所があって、定期的にそこにいろんなお坊さんが座って、何か出来るようなところがあればいいのではないかと、つくづく思います。 医療の面だけではなく、生活の中に入ったそういう法を説くということができるのではないかと思います。
先ほども、法律上というお話をされていました。 医療裁判が多いですが、でもおもしろいものです。 でも相続を争うのはお墓の前が結構多いのです。 証人にお坊さんがいるからということがあるみたいです。 ですが、おもしろいのはそういうことではなくて、非常に故人の世話をしてきた人はなにもしゃべらない。 世話をしてこなかった人に限って主張してとうとうとしゃべる。 本当に世話をしてきた人は「足るを知って」いるのかもしれません。
この会で、知足ということによって、何か生まれる、発展的なものがないかと考えていますが、足るを知るということは、己を知るということです。 ただ、病気に明日なったとしても、いつまでも、刺激と感動と目的を常に持っていると、あまり簡単にぼけないとおもいます。 あまり力説しましても、我が身に降りかかりますがね。 いかに自分を充実させ、今に生きるべきかと言うこと。 その中にも経済力もあるのですが、たとえば、こういう所に参画できないほどの経済力の方も多くおられるので、そういう方をどういう風に豊かな心を持ってもらえるかということが、仏教会の立場から言うと、戦いになるとおもいます。
最後になりましたが、もうひとつ。 昨日お寺に3人でみえられて、一人5分位ずつ、みなさんお話されるんです。 3人ともに物語があるのです。 この物語を聞いて吸収して、なにか健康を図る、安堵の道をさぐるのはできないかと。 患者さんも物語をもっていますから、その物語を聞いてあげて、回答が出せるものは出せるとしたら、そういうことを連続していけば、すこしは変わるんじゃないかとおもいました。 そんなことでございます。 どうもありがとうございました。
西村
ありがとうございました。 4人の方の良いお話をおうかがいいたしました。 今、北園さんがおっしゃったように、この会の大事なキーワードは「知足」でございます。 最初に、お話をいただいた4人の方々に質問などございましたら伺いたいとおもいます。 いかがでしょうか。
対本
それでは、音羽病院の松村先生にお伺いしたいと思います。 今日ここには僧侶がたくさんおりますが、ホスピスや緩和ケアで、僧侶がどういう風な関わりを持てるだろうかと言われますが、医療側からは、単純素朴な回答として、それは無理だ、需要がないという声が聞こえてきます。 時に、「どうぞ来て下さい」と言われるのは、リップサービスかもしれません。 先生のお立場から言って、もっともシビアで、お世辞もなにもないところで、もし、僧侶が、ある程度の熱意があって、ある程度知識があるとして、そのような人間が本当に役に立つとおもわれるか。 たとえば、「患者と医療スタッフの隙間を埋める」という表現がされますが、本当にそうなのか。 もし、ヒントにあるようなことがあれば、お教え頂きたい。
松村
きょうのスライドの最後でもお見せしました、「人生経験に富む医療者(宗教者)が半歩出て死生観を漏らす」というところですね。 先ほどのお話にもありましたが、「わからんもんは、わからん」ということがあります。 みんな、死んだらどうなるか、それは「わからんもんはわからん」のです。 死んだことはないのですから。 そういうことを、人生経験に富む人が、患者さんにお話していただけるだけで、患者さんも家族も救われると思うのです。
日本の高齢者は、90%程の方が、枯れ木のように亡くなっていき、またそんな時代にさらになっていくと思おうのです。 いろんな点で、「わからんもんはわからん」と言ってもらえるような、特に終末期には家族を含めて、そのような接触があってもいいのでいかと
実は7年前に亡くなった自分の父の死の話をしますと、4年間の闘病と2年間寝たきり状態で、鼻からの経鼻胃管を挿入し、それを嫌がったまま亡くなりました。 私も嫌な方でしたし、父本人も、母も妹も、それを嫌だとしながらも、外すこともできず亡くなったのです。 結局、介護についていた妹が一番嘆くのです。 私は、経鼻胃管を入れようと、若干命が短くなって亡くなろうと、全部往生だと勝手に思っております。 どの道を踏んでも、いろんな往生の仕方があり、どの死も往生だと。 そういう応用力のある対応が、救いを求めている者には似つかわしい。 お葬式の時に、「この死は往生だったんだ」という、わかりやすい言葉が出て欲しい。 難しい話でなしに、この死は往生の死であると言って頂ければと思うのです。
対本
ありがとうございます。 北園さんがおっしゃっていたように、「わからないものはわらない」という、いかにも禅僧のお坊さんらしい発想ですが、それがなぜ医者が言えないのかとおもいます。 言葉は選んでもいいんですが。 患者さんの心に響くようなことが、言えないか。 私も現場にでていて、医師も看護師も本当に忙しいし、そういうことを話す暇もないですし、それは無理と言われればそうかもしれないのですが、若干、そのようなことをみる余裕がないかとおもうのです。
2番目におっしゃったことですが、それは大変大事だと私も思います。 私はまだ先生のように経験がないですが、患者さんの中には、悔いが残る、周りの家族も悔いが残っていると見受けられることもあります。 でも宗教者としてみれば、私は、どの患者さんの死も、その死はパーフェクトだと思うのです。 ご家族にもそういう話をしてきました。 死というものは、プロセスですから、死の前後で決まるというものではありません。 死は緩やかに続くプロセスの中でトータルとして見ていかないといけないのではないかと。
時には、人がいないときに一人で死にたいと言われる方もいます。 ある患者さんは、お兄さんが15分間、電話を掛けに行ったその瞬間に亡くなられました。 その方の手をとって死亡診断をしたときに、私は「すごいじゃないですか。 完璧じゃないですか」と。 その方にとって、一人で亡くなるということは、その方の魂にとって必要な事だったのだろうと。 これは、僧侶的なものの見方になるわけですが、命は、計らいを超えたところにあるわけで、良い死、悪い死、悔いが残るというより、ゆるやかな時間の流れの中であるものだと思います。
では、つづいて法律の先生、樋口先生にお伺いしてもいいでしょうか。 アメリカの医師国家試験の試験問題がでていましたが、私もこのような試験をうけたことがあり、大変だった記憶があります。 また、同じような質問をさせて頂き恐縮ですが、お坊さんが医療に関わるということは、法律的には何も問題はないとおもうのですが、何かご指摘をいただければありがたいのですが。 たとえば私は、死というものは、非常に曖昧なものを含んでいると思っているわけです。 自発呼吸が停止し、心臓も鼓動を止め、瞳孔も両眼とも対抗反射がないと、それを確認して死としていますが、ただ、何時何分という時間的な一点では決められなくて、周りの状況とか、家族が来ていないから、あと5分待とうとか、そんなこともします。 そういう点でも、死は曖昧さもあるのではないかと思ったりします。 そういうなかで、医療過誤ではないのですが、我々の対応の甘さもあって、不信感をお持ちになられ、最後の死亡診断でカルテの呈示を求められたこともあります。 病院が対応しましたし、医療者として個人的にはどうということはありませんでした。 ただ、法律はもう少し頭に入れておかなければならないと思ったわけです。 あいまいな質問で誠に申し訳ないのですが、お坊さんが医療の何かに関わるとして、そこに対してご指摘があればありがたいと思います。
樋口
お答えできるかどうかわかりませんが、何年か前に、アメリカの本の翻訳書で「患者の権利」という本が出ました。 昔からある厚い本ですが、その新しい版の翻訳が出たという事なんですが、その中で、医療というのは何なのだろうということで、わかりやすく3つの比喩を提示しています。 「~であるかのように」という比喩です。
まず、伝統的な比喩は、戦争の比喩です。 何と戦っているかというと、病と死に対して戦っているのです。 しかし、生き物なんて、いずれは死ぬので戦争の比喩を使っている限りは負けるわけですが、負けるまでは負けてはいけないのです。 最終的には負ける、死ぬのですが、負けないように徹底的にがんばるわけです。 しかも医療技術が進んできたので、どんどん軍備も増えてきたわけです。 ありとあらゆるものを使って、とにかく少しでも伸ばすということができるようになり、軍備拡大で徹底的にやるということになります。 ただこの比喩を使っていくと、患者は辛くなるのです。 なにしろ、戦場は患者ですから、指揮官は医師で、負けちゃいけないと、一生懸命やるわけです。 でも、アメリカの先生もそれはおかしいのではと言っていて、アメリカの医療倫理のなかではもはやそれはないのです
2つめの比喩は「マーケット=市場」です。 患者は消費者として医療サービスを買います。 医者はその提供者、売り主です。 いろんな要求を患者は出して、それに答えるのが医療だという考え方です。 いま、アメリカでは、この議論が最も影響力のあるものとして行われています。 患者は消費者ですから、情報もたくさん入れなければいけません。 しかし、これもまた限界があるとおもいます。
そこで、3つめの比喩は、「エコロジー」です。 問題は、そのエコロジーという比喩のなかで、具体的な医療の問題で何が出てくるかというところが今後の課題です。 これは米国においても、日本においてもいえます。
たとえば、人工呼吸器を一回つけたら外せない。 これはまさに、戦争を続けないといけないという比喩に通じるものがある。 これは、アメリカよりむしろ日本にその傾向が残っている。 そしてその後ろに、刑法とかが乗っかってきている。 それだけでなく、医者だけでなく、人々がまさか戦争が大好きなのだとは思いたくないのですが
また、アメリカでも、終末期医療の面で倫理委員会を立ち上げることは大いにあるはずです。 その中で、日本と違うのは、その倫理委員会に宗教者が入っていることはごく一般的なようです。 そういう会で、特定の患者さんについて、どういう死なせ方、というか、余命の過ごし方を、医療関係者だけでなく、宗教者が入り、法律家が入りソーシャルワーカーや一般の地域の人がはいって、考えてあげるということです。 日本でも、プロセスガイドラインのところでお話したように「一人だけで判断しない」ということがありましたが、人の生死を決めるという事は、大変なことですから、慣れていると言っても間違えることがあります。
やはりひとつの道は、どこの病院でも、終末期の人がおり、その人たちについて、何か出来ないか相談してみようというチームづくりをやってみるのはいいのではないかと思います。 たとえば、京都なら、病院の近くにたくさんお寺があるわけなので、そういう人に入ってもらうということをしてみれば良いと思う。 法律家を入れるより、ずっと良いのかもしれません。 その時に、医療ケアとは、誰をケアするのか。 患者はもちろんですが、家族にもケアをするのもあるでしょう。 また、医療者だってケアが必要です。 たとえば先ほどの戦争病にかかっているのだったら、宗教者が「戦争はこれぐらいでやめたらいかがですか?私はいろんなケースをみています」というような話をしてあげられるかもしれない。 患者本人だけのケアではなく、医療ケアチームをつくってみるのも、本当はあってもいいのではないかと思うのです。
西村
ありがとうございます。 樋口先生の話で、思い出した話があります。 今から30年ぐらい前に、阪大の中川●●先生から医療の勉強をさせて頂いたのですが、その時に中川先生が、こういう事をおっしゃっていました。 昔は、医者はシャーマンだった。 つまり、技術士だった。 しかし今、サイエンスがますます発展したので、サイエンスに基づいて科学者になってしまった。 でも今、本当に必要なのは、援護者なのではないかと。 おそらく、当時の病院は、昔は、主人公はお医者さんでしたが、周りをそれが手伝う感じでしたが、今の医療の現場は、チームとして進んでいる。 サッカーにたとえると、シュートする人はお医者さんでなくていい。 MFぐらいでいい。 時にはシュートもしたり、ディフェンダーとして守ることもする。 そのときに応じて、いろんな役割を果たしてほしい。 私が宗教者に期待するのは、DFかなあと思っている。 本当は病院に聞けないことがたくさんある。 「お医者さんはあんな風に言っているけど、どう思うか?」と、お坊さんと相談してみるのはどうか。 とにかく、いろんな役割を果たすという中で、今回の主旨は、特に、お坊さんにこの終末の医療を考える役割を何か果たしてほしいと思いました。 さてここで、主催者のお一人でもあります中野東禅さんにも、少しお話を伺いたいとおもいます。
中野東禅
昨年からお話をしてきて、「知足」ということが、一つにあったわけですが、今日、お話を伺いまして、中心の課題とつながっていくことが出来たのではないかと思っています。 また、みなさんにアンケートを集めて、今日集計の一部をお配りしたのですが、それらと今日のお話を考えると、この問題が、法律の問題、家族の問題と各立場で様々な問題があって、それを統合する形で、 知足という哲学を提示することにより、現場とどう関係し合って問題を解決してけるかというのが、この研究会の課題であったかとおもいます。 今日伺っておりまして、これがある程度整理がつくのではないかと。 またアンケートでも大変丁寧な言葉を頂いておりますので、それらを踏まえてみると、こういう作業が今後可能だなと感じました。 法律の問題にしても、家族の問題にしても、そう感じたので、一つ希望が開けたというか、こういう風にまとまりが付くんだなあと感じさせて頂きました。 そして、次は委員会、委員の課題なんだなとかんじました。
佐藤(京都大学大学院)
非常に勉強になり、来させて頂いて良かったと思っています。 樋口先生のプロセスガイドラインの中にも、終末期医療を考える上でも、心のケアを入れないといけないだろうとおっしゃっていました。 私も本当にそうだと思います。 9月に名古屋でありました医学会に行きましたときに驚きの発言がございまして、精神科のドクターは、終末期の癌患者さんが「死にたい」とか「早く殺してくれ」といった発言がでると、うつの傾向があるとして、薬剤を選択する。 しかし、終末期のうつの傾向には抗うつ剤は効かないと、ドクターが平然と言っていました。 しかし、そんなことは当たり前だろうと一般市民としては思うわけです。 医療の世界のなかのスピリチュアルケアというのは、宗教とか、魂とか、霊という意味ではなく、私の中の存在とは何だろう、私がこうやって生きている意味は何だろう。 死んだ方がいいんじゃいかとか、家族に迷惑をかけてしまうとか、そういった苦悩を抱えていることが、スピリチュアルペインと言うのだと言われております。 そういった、存在論的な苦悩をどう癒すことが課題となっているのです。
そうすると、対本先生の話にもつながるのですが、宗教者は何ができるかと。 出来ることはあるのにと、先ほどから聞いていて思っていたのですが、樋口先生もおっしゃっていましたが、私はホスピスに行っている時に、宗教者の方がいらっしゃって説法をして帰られました。 それを聞いた患者さんは、「またたくさん説法して帰られた。 お坊さんは、言いたい事を言って帰る」と話しておられました。 そこで思ったのですが、患者さんは、話を聞いてもらいたかったのです。
宗教者の方がやってきて、「今日はどう?」と聞き、「そうか、そうだったんだね。 」と、聞いてくれるだけで、患者さんがどれだけ助かるか。 お医者さんが来てくれるのもいいのですが、はっきり言って、衣を着てくれたお坊さんが来てくれて話を聞いてくれたら、どんなに心が癒されるかと。 そう思うわけです。 宗教者が衣を着て病院に入れないというのが、そもそもおかしい。 その環境を、医療そのものが変えていけば良いのではないかと思うのです。 ですから、対本先生に対しては、聞く側にまわるという事が必要ではないかとおもうので、その辺をいかがお考えかと思います。
対本
ありがとうございます。 素晴らしいご指摘です。 実は、それを、私からではなく、皆さんの方から言って頂きたいのです。 衣を着て入ってもいいのではないか?というのは、それは、わたしから言ってもあまり価値がない。 皆さんから言って頂けるのがいいです。 そして、皆さんの意識も変えていってほしいと思います。
西村
良いコメントで、良いお答えでした。 では、時間が来ました。 では、このシンポジウムはこちらで一度終わり、対談へ移りたいと思います。