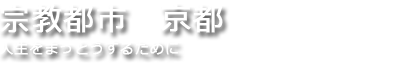第1回 医療と宗教を考える研究会/メッセージの詳細ページ
第1回 医療と宗教を考える研究会
日 時 : 2010年8月24日(火)13時~17時
場 所 : 相国寺承天閣美術館2階会議室
【参加者】
大谷 昌弘(立命館総合企画部次長)
川分 陽二(フューチャーベンチャーキャピタル㈱社長)
北園 文英(京都仏教会理事 円通寺住職)
坂口 博翁(京都仏教会理事 覚勝院住職)
佐分 宗順(京都仏教会評議員 相国寺教学部長)
塩田 浩平(京都大学副学長)
篠原 総一(同志社大学教授)
泰井 俊造(薬師山病院院長)
田中 滋(龍谷大学教授)
津村 恵史(中外日報社論説委員)
中野 東禅(曹洞宗総合研究センター講師 龍宝寺住職)
長澤 香静(京都仏教会事務局長)
西村 理(同志社大学教授)
西村 周三(京都大学副学長)
二宮 清(洛和会丸太町病院院長)
浜本 京子(日本バプテスト病院)
堀場 雅夫(堀場製作所㈱最高顧問)
増田 寿幸(京都信用金庫理事長)
松村 理司(洛和会音羽病院院長)
宮城 泰年(京都仏教会常務理事 聖護院門跡門主)
森 清顕(清水寺録事)
森島 朋三(立命館常務理事)
森本 均(㈱DAC社長)
山岡 義生(日本バプテスト病院理事長)
横江 桃国(京都仏教会評議員 養徳院住職)
吉田 清順(京都仏教会評議員 教泉寺住職)
吉田 忠嗣(吉忠㈱社長)
渡部 隆夫(ワタベウエディング㈱会長)
(五十音順)
【事務局】
長谷川和子 大島祥子(京都クオリア研究会)
徳久恵里(京都仏教会)
■はじめに
長谷川
本日はお暑い中、「医療と宗教を考える研究会」にご参集いただきありがとうございます。日本では、長い不況からの出口がまだ見えない状況ですが、20世紀の大量生産・大量消費型の社会から21世紀型の感激・感動ある社会づくりを推進しようと、3年前に、研究者を中心に京都クオリア研究会が発足しました。新しい価値の創造には、京都の哲学、宗教を生かすことが必要と、今年度、京都仏教会とともに「宗教都市・京都を考える会」をスタートさせました。そして、初年度の取り組みとして「医療と宗教・仏教を考える研究会」を立ち上げたものです。
日本は、世界のどの国もが直面したことのない超高齢社会に突入しました。30年くらい前までは自宅で亡くなる人が多かったのですが、近年はほとんどが病院で亡くなる時代となり、福祉の問題だけではなく、クオリティオブライフの観点からこの高齢者医療を捉えることが求められています。
誰でも迎える死ですが、医師に任せっぱなしになっていないでしょうか。今後は医師、宗教者、家族がいかに向かい合っていくかが問われてくると思われます。第1回は、長年終末期医療に携わってこられた曹洞宗総合研究センターの中野東禅さんを招いて勉強会を開催しました。
今回は、「命のリレー」を考え、賢く看取るためにどうすればよいかを考える勉強会です。会場には、医療界、産業界、そして研究者の方にご参加いただき、この超高齢社会をどう受け止め、それぞれが補完しあう関係をどうつくるかにについて踏み込んだ意見交換ができればと願っております。
■あいさつ

有馬頼底 (臨済宗相国寺派管長)
仏教は人の死とは不可分です。人は生まれ、老い、死にます。これは避けることができません。だからこそ、この世の存在する生命は輝きを持つのです。では、人の死についてはどうでしょうか。先日、脳死による臓器移植の三例目が実施されましたが、これは本当に良かったことなのでしょうか。色々と疑問を持っています。
私は二人の大先達を見送りました。亡くなった時からお葬式まで時間がありますが、その間にも毛が伸びるのです。最後の剃髪も私がさせていただきました。静かな自然死でした。師匠は、亡くなる10日ほど前から「私はそろそろ死ぬよ」と笑いながら話されました。「私のことは、私が一番分かるよ」と。そして、15日後に静かに逝去されました。これは、禅宗で修行していることだから分かることなのでしょうか。そうではありません。私もお見送りしましたが、本当に自然に亡くなりました。
今日は宗教と医療という大きなテーマの研究が始まるスタート地点です。どうぞよろしくお願いします。
■講演
(1) 祈りとつながり
大井 玄 (東京大学名誉教授)
1935(昭和10)年 京都府生まれ。 東京大学医学部卒業後、ハーバード大学大学院終了。
東京大学医学部教授、国立環境研究所所長などを歴任。著書に「終末期医療」「痴呆の科学」「いのちをもてなす」「『痴呆老人』は何を見ているか」「環境世界と自己の系譜」など。
現在も都内で高齢者の診療に携わるなど、臨床医の立場から終末期医療に取り組んでいる。
「終末期の祈りと念仏」

この席には研究者、宗教者、医療に携わる各方面の方、信仰を持つ方、無信仰の方も参加されています。私は医療行為をするとともに、医療における宗教行為も日頃から観察しております。本日は、宗教にかかわる心理的働きがどのように成立するのか、その側面に触れたいと思います。その際には、近年の脳科学の知見も含めたいと思います。私は終末期医療に携わっておりますが、終末の差し迫る状態にある人は、超越的なものにすがりたいという心情があるのをしばしば観察しております。超越的存在とは、先祖や子孫、共同体、宇宙、神仏をさします。
私が診療する90歳の女性は、20数年前に夫を亡くし、入浴にも介助を要するような状態ですが、日々仏壇の前に座っております。彼女は仏壇に法華経をあげるのです。他の九十歳代の女性は腰痛や大動脈弁狭窄のために外出もできませんが、般若心経の写経をされています。写経には念仏同様、超越者と繋がる感覚があると思います。私の母は終戦後、経済や家庭の苦しみから逃れるためにカソリックに改宗して晩年はマリア像に祈っていました。緑内障で目はほとんど見えなくなりましたが、そこにはどのようなマリアが映っていたのか、と考えたことがあります。私はキリスト教徒ではありませんが、母について確かだと思ったのは、祈りが、彼女にとっては非常な慰めであったのということです。
そこで、素朴な疑問が生じます。「神、仏は客観的な存在か」ということです。明治時代には清沢満之(東京大学の哲学科を首席で卒業した宗教家)は論文「科学と宗教」において科学的思考の限界を指摘し、論考「宗教は主観的事実なり」を表し、宗教に客観的事実性を求める態度を退け、「私どもは神仏があるから信ずるのではなく、私どもが信ずるがゆえに私どもに対し神仏が存在する」と断言しました。宗教は心的な実在であるということです。これは心霊的、スピリチュアル、といったほうがわかりやすいかもしれません。
清沢と同時期のウィリアム・ジェイムスも同様な主旨を述べています。「宗教的経験の諸相」において、宗教の発生についての「事実判断」と、成立してしまった後のその人にとっての意味、価値を問題にする「価値判断」を峻別すべきだ、と主張しています。
「神の『文化的進歩』」
神を歴史としてみると、科学的実在論者にとっては理解できないことが多数起きています。それは、神が文化的成長進化を遂げてきた事実です。今の人類は、遺伝学、考古学などの科学的知見によれば、65,000年ほど前にアフリカからユーラシア、南北アメリカなどに広がってき行きました。
狩猟採集の世界においては数十人から百人位の集団で構成されていましたから、情報の共有も容易で、集団への忠誠心、相互利他的な倫理意識で平等な社会生活でした。そこに農耕が始まり、社会集団が大きくなると、富や権力の格差が生まれ、集団同士の対立がうまれます。そしてそこに集団を守る神が誕生します。宗教学者のロバート・ライトによれば、一神教の神ヤハウェは文化的な進化を遂げてきたといいます。最初は人間くさい神であったようです。紀元前3世紀の七十人訳旧約聖書や死海文書の研究からして、戦闘的で嫉妬深くて残忍な神で、「申命記20」に記されるように、「男子を剣にかけ、家畜や女は全て奪っても良い」とか「息のある者は一人も生かしておくな」と自分を崇める民に猛烈な指示を出しています。現在ならジェノサイドであります。しかし歴史の経過と共に神は性格を変えてきております。ライトによれば、ひとつには文書的表現に曖昧さがあったことから、後世の恣意的解釈の拡大、改ざん・無視が可能であったということです。このような恣意的な改変は世界の宗教において繰り返されてきました。田川健三氏のように、「神を信じないクリスチャン」が現れてもおかしくありません。
イエス・キリストの言行は4つの福音書にまとめられましたが、当然人為的所作が入っています。もっとも旧いマルコ伝や、マタイ伝、ルカ伝の著者が参考にした資料には出ていない話もあります。イエスが最後の審判はもう直ぐ来ると予想しているのは宗教学者の一致した解釈ですが、イエスは近づく神の国はイスラエル人だけのためにあると考えていたようです。後世の福音書の編纂の過程で慈愛を持つ万人のための神の性格に変化していきます。
一神教への態度には大きく3種類あり、一つは宗教の発生や成長過程を進化論的に解釈することで、これは無神論にあたります。「利己的遺伝子」や「神という妄想」の著者リチャード・ドーキンスが典型です。彼にとっては一神教はおとぎ話に過ぎないのです。もう一つはコーランや聖書に書かれていることは全て正しいとする原理主義的立場。これによると1万年ほど前に人は創られ、そこから変わっていない。これは「若い地球創造説」と呼ばれ、現在まで何度もアメリカで調査が繰り返されていますが、アメリカ人の半数近くがこれを信じています。2008年のアメリカの大統領選で有名になった共和党副大統領候補のサラ・ペイリンもそうですが、進化論に賛成する人はわずか10数%しかいません。宗教的原理主義者がこのカテゴリーにあたります。そして3つめが中間のジェイムスのような人で、事実判断と価値判断を分けて考えるべきだ、という立場です。宗教は主観的、心的な事実であるという清沢もこれに入ります。
「事実判断と価値判断の混同」
文化人類学者のクリフォード・ギアツは、「人は自分の紡いだ意味の網に宙ぶらりんになった動物である」と指摘しました。これはそのシニシズムを除くと、「人は自分が紡いだ意味の世界に生きている」と換言できます。「意味の世界」は、ハーバード大学の認知心理学者スティーブン・コスリンのようにこれを脳科学的に表現することも可能です。「人は見るもの、聞くもの、触るものから世界が構成されていると思っているが、脳は経験(閲歴)と記憶から世界をつくっている」。脳は世界を経験と記憶を使って何であるかを理解しているのです。これは、認知心理学では常識になっていますが、すぐに確かめることもできます。たとえば、私は現在この会場で皆様にお話ししています。「私」「現在」「会場」「皆様」「話す」などの言葉はすべて私が経験し、記憶しているものであって、もし記憶されていなければ、私が現在経験している世界は存在しません。また「意味の世界」を理解するには、認知能力の喪失により、私たちがいる世界とのつながりを断たれた人々の言動が参考になります。
元東京都精神医学研究所長の石井毅氏は、八十歳代のかつて料亭を経営していた女性が、病棟を料亭と認識して、ナースに「コーヒーをお出しして」「日本間を掃除して頂戴」という命令をする症例を報告し、これを「仮想現実症候群」と名付けました。長野県立看護大学学長阿保順子氏は、私が知る限りでは最も優れた仮想現実症候群についての医療人類学的観察記録を残しています。それは認知症の人々がどう自分達の住む場所や人を理解しているのかの長期にわたる克明な観察記録です。この報告は、私たちの認識と認知症の人たちの認識がどのように異なっているのか、彼らがどのような「意味の世界」に住んでいるのかを明らかにしました。しかしながら私たちは、認知能力が衰えていなくても、それぞれの「意味の世界」に住んでいる事実には変わりがありません。
「『意味の世界』という世界仮構」
例えば、その事例をジョージ・W・ブッシュ前アメリカ大統領に見ることができます。9.11のテロの後に、実際に関わりのないイラクのサダム・フセイン大統領がアルカイダと「つるんでいる」と認識して、イラク侵攻を行いましたが、その際に「十字軍」と口を滑らせました。このキーワードから、彼の「意味の世界」ではキリスト教とイスラム教の対立が、現在でも進行しつつあるのが伺えます。しかもCIAのもたらす錯綜した情報を自分の「意味の世界」に適合させるために恣意的に取り入れていました。
「意味の世界」は、私たちの脳が仮構をするのです。その事実を最初に指摘したのは、今から1600年も前に唯識の心理学をつくった世親、無着などの大乗仏教僧でした。宗教者の方に唯識についてお話しするのは、完全に釈迦に説法ですので、これ以上は申しませんが、唯識では、深層意識の最下層にアーラヤ識があるとしています。「唯識三十頌」第一頌では、「自我と存在の相は、(アーラヤ識により)仮に想定されたもの」と述べている。それの脳科学的現代訳は、「脳(アーラヤ識)は身体的世界の心的(精神的)モデルを作っている」ということです。
この唯識の認識は、脳科学的理解と根源的に一致しています。どのように脳が心的世界を創造しているのか、認知心理学者クリス・フリスは「世界のでっち上げ」(「Making up the Mind:How the Brain Creates our Mental World 」,Blackwell Publishing 2007)と呼んでいます。少し長く引用しますと、「本書では精神的(mental)、身体的(physical)という区別が誤りであることを示そう。それは脳が作り出した幻想(illusion)だ。身体的世界、精神的世界のいずれであろうと、われわれの知る全ては脳を通じて意識される。-(中略)-脳は、それが行う全ての「無意識的推論」を隠すことによって、身体的世界の事物とわれわれが直接接触しているという幻想をつくりだす。この幻想を通じて、われわれは自分が独自に世界に働きかける行為者であると感じている。しかも世界について自分の経験を分かち合う能力は、ヒトの脳の働きを変化させ、その文化を生み出してきた。」と記しています。
「アーラヤ識と脳」
ここで脳をアーラヤ識に置き換えると、現代の唯識になります。「無意識的推論」は19世紀の偉大な生理学者ヘルムホルツの造語です。ものに触って感ずるには、100ミリセコンド以上の時間がかかります。その間に脳が推論をしていると彼は考えました。脳の行う仕事の95%以上が無意識に行われている、というのが脳科学者の一致した見解です。外界の刺激を受けて推論して、それを伝えています。意識に伝えるにしても、推論を伝えているのです。精神と身体世界の違いは、脳により作られた幻想なのです。
例えば機能的MRIは、脳の特定場所の血流量を見て脳がどういう反応をしているか調べることができます。意識しなくても脳がどう環境状況に反応しているかを知ることができます。
例えば最初に怖い表情の顔写真を見せて、すぐに普通の表情の写真を見せると、大脳の中心を囲んだ辺縁系のアミグダラと呼ばれる神経細胞群が強く活性化されます。しかし短時間なので怖い顔を見たという意識は起こりません。潜在的に危険で怖い環境情報が意識にまで伝えられなくても、脳はそれを認識しているのです。唯識の学僧たちは、深い瞑想体験に基づいてアーラヤ識とマナ識という無意識を考えましたが、脳科学の発達は彼らの洞察が本質的に正しいことを裏付けています。
「『意味の世界』は主観的世界、病気と宗教体験」
「客観的事実に基づかないものは信じられない」という人は、病気体験や宗教体験にかかわる心理のことなど、信じられないでしょう。私たちが紡ぐ意味の世界は、主観を構成する我々の記憶や期待、価値観により既にゆがめられています。認知能力の衰えた人が仮想現実症候群を示すのには驚かされますが、それは状況評価において主観と客観の食い違いがあること、言葉の性質によります。
医療人類学者のマ-ジョリ-・カガワ=シンガ-が行った調査では、癌患者50人の聞き取り調査をして、常識的には信じられない観察をしています。癌に対して闘うものだとイギリス系アメリカ人は認識しているのに対し、日系アメリカ人は知っていても知らないようにして堪え忍ぶ、という文化差があります。しかし50人中49人が「自分は健康だ」と答えているのです。そのことから彼女は「我々は健康に死ぬことが可能だ」と考察しました。
宗教体験はさらに多様でして、常識的合理主義者が単に「幻想だ」と思う事例を、ジェイムスは「宗教的経験の諸相」で記載しています。例えば四十九歳の男性の次の手記ですが、ジェイムスは「敬虔な人であれば、おそらくほとんどが同様に感じているだろう」としています。「神は私にとっていかなる思想、事物、人物よりも実在的であり、神の現前を感じ、(-中略-)日光の中にも雨の中にも神を感じる。神をたたえる時は、友人に語りかけるようにする」と。彼らの紡ぐ意味の世界には、生き生きとした心的体験があることが伺えます。宗教の価値や意味は、こうした体験に裏付けられたところにあるのでしょう。
なぜこのような心的体験が可能なのでしょうか。それを可能にする神経生理的知見が近年明らかにされてきました。それはアーラヤ識、つまり脳が身体的世界のメンタルモデルを作ることができることに由来します。目に見えないものをイメージできるのです。私の母が祈りの中で聖母マリアを思い浮かべたり、患者さんが仏壇の前で亡くなった夫の顔を思い浮かべることがありますが、このような行為は現実に可能であるという脳科学的知見が出されています。
実際に顔を見たり、心に思い浮かべるのと建物や場所を見たり思ったりするのでは、脳の中で活性化されるところが異なります。思い浮かべるときの方が実際に見るよりも活性化は弱いですが、見ることと思い描くことの違いは、心を刺激する生々しさに過ぎないのです。
脳が心の中で身体的世界を描くとき、直接関わっているのがミラー・ニューロン、つまり鏡神経細胞と思われます。1995年にイタリアのリゾラッティたちが見いだしたもので、一言でまとめると、私たちの見ている他人の行為は、全て私たちも心、脳の中で行っている、というものです。偶然に見つかったものなのですが、あるとき神経学者が猿の脳に微小電極を入れて、ものを食べるときの興奮状態を見ていた。猿が食べ終わったとき、別の研究者が入って来て、残っていたピ-ナツを食べた。猿はそれを見ていただけなのですが、猿の脳神経は自分が食べるときと全く同じ反応を示したのです。つまり、他人がしたことを見るだけで、自分がしているかのように脳が反応したのです。
「見る、思い描く、共感する -認知心理学的知見-」
これにより他者の行為を真似たり、行為の意図を理解したり、行為に伴う感情を共有することができるのです。また、私たちには共感する能力があります。他者を思いやり、感情を共有することもできます。つまり他人が経験する知覚上の痛み(sensory pain)は感じませんが、自分の妻や子どもなどについては、情動的痛み(affective pain)、精神的な痛みを感じます。機能的MRIで観察すると、知覚的痛みと精神的痛みでは、脳の少しずれた所で反応していることがわかります。精神的な痛みについては、自分のものも愛する他者のものも実に同様に反応するのです。共感性の高い人ほど他者の苦痛に対する反応が強くなります。共感、慈悲、慈愛の痛みということができます。「あなたを愛するが故に、あなたの苦痛を感じている」と、十字架にかけられるイエスを思えば、彼の苦痛を感じることもできるのです。
「朱に交われば赤くなる」
仏の慈悲、マリアの慈愛を思うことは、それだけで思い浮かべる人の行動に影響します。象徴や観念には感染性があるのです。慈悲や慈愛はそれです。ウィリアム・ジェイムスはその心理学において、ある観念に引き続いて運動が滞ることなく行われる場合を、観念運動(ideo-motor action)と定義しました。例えば職業的ピアニストは指の運動を意識することなく自動的に演奏をします。無意識性、自動性に観念運動の特徴があります。もう一つの特徴は、影響の力、無意識的感染性です。多くの心理学者がその側面を観察しています。例えば、学生に文章構成能力テストを行うとカムフラ-ジュの説明をした後、高齢者の身体的、社会的特性を構成する単語を読ませただけで、老人のようにゆっくりと動きます。もちろん彼らはそれを意識していません。別の実験では攻撃的、恥知らず、等という言葉を読ませると、無意識に学生たちはそのような言動をします。私たちが関わりある人にも感染性があり、その人のことを考えるだけでも知らず知らずその人に似るようになります。そしてその人が次にどう行動するかを予測することができます。つまり人はその理解する阿弥陀やイエスに同化できるのです。
「まとめ」
神仏は、信じるから現前するという心理的メカニズムが明らかにされつつあります。脳つまりアーラヤ識は身体的世界を心の中のモデルとして仮構し、作ります。脳はミラー・ニューロンにより他者が行う行為の意図を察したり、真似たりすることができます。身体的な痛みは共有できませんが、メンタルな痛みは共に体験できます。そしてその程度は愛や思いが強い方が、強くなります。
祈ることで神仏に自分を同化させることもできます。人生の終末にかかる人、一人で世を去ろうという人が、超越的なものに繋がりたいという願いは自然なことでありましょう。日々の念仏や祈りに繋がる対象を思い描き、イメージを強めていくことは、繋がりを強めるという心的行為です。意識上の表象は、脳の中の深層意識的働きに支えられています。現在、一人で暮らす老人が増えている中、繋がる宗教的な対象を見つけて安心していることは大事だと思います。
(2) ホスピスの現状 ~経営的視点に加えて~いきいき生きる~
田辺親男 (親友会グループ会長、京都経済同友会代表幹事)
1947(昭和22)年 京都市生まれ。京都府立医科大学卒業後、大学付属病院に在籍、1979(昭和54)年に個人医院を開業。現在は、循環器専門の島原病院、ホスピス病床50床という日本最大規模のホスピス・薬師山病院、人間ドックやPET画像診断の坂崎診療所などを有する親友会グループ会長。医療界では初の京都経済同友会代表幹事を務める。

大井先生からは哲学的なお話も頂戴しましたが、私は、医療の現場にいるものとして、現実的なお話をさせていただきたいと思います。
私は、もともと放射線科にいましたが、その当時は人体の断面を3分かかってスライスしていました。今はもっと技術は進歩していますので隔世の感があります。そこから治療の方に回り、その医療の現場で感じたことを通じて、ホスピスの必要性を感じていました。
薬師山病院はホスピス専門の病院ですが、ここができたときに「理念」を作りました。 その理念は、「『やくしやま』は、患者と家族 スタッフとボランティアが、それぞれの生き方を尊重し充実した生活を過ごす家である」という内容です。この理念を作ったのは開設時の今から16年前です。もともとこの病院は昭和15年にできたもので、結核の自然療法を採用していた病院でした。つまり、免疫力を上げる療法を採用していました。私がそこの後を引き受けたのですが、その際にホスピスをやろうと考えました。
16年前当時、癌で亡くなる方で「家で亡くなりたい」という方は約9割おられました。現在でもその割合は8割近いです。多くの方は自宅で療法をやりたいのですが、急変への対応、そして家族に迷惑をかけたくないという思いから、それを断念されています。そのようなことから、理念をこのような内容にしました。私たちはあくまでも「家」にこだわりました。病院開設後3年間は経営の苦しみを味わいました。
基本方針は、「①『やくしやま』は、痛みなどの不快な症状の緩和につとめ患者と家族がその人らしく生きられる家である」、「②『やくしやま』は、ケアを始めたときから、死別後まで患者と家族へ全人的ホスピスケアを行う家である」、「③職員とボランティアは、患者、家族と共に生き、学び、よりよいケアを提供する」としています。
スタッフは、医師が6名、看護師が36名、看護助手が7名、音楽療法士兼ボランティアコーディネーターが1名、管理栄養士が1名、医療連携室が3名、事務が9名、登録していただいているボランティアは45名の合計109名の体制です。50床で日本最大のホスピスですが、現在は30床で回っています。このスタッフ数では、満床では回せない、という事情があります。
ホスピスを立ち上げた当時はバプテストでされていたくらいでした。当時はホスピスで亡くなった人の9割が仏式の葬儀をあげていましたし、それは現在でもほぼ変わっていません。今日に備えて葬儀社に葬儀に関する状況について訪ねてみましたが、家族葬が増えてきていますので、客単価は減少しているそうです。
<写真による紹介>
- 比叡山を眺める自然環境豊かな立地
- 玄関と受付
- 緑豊かなA棟
- ステーションとカンファレンス。垣根をなくし、医師は私服を着用
- 2階サロン。ここで様々な行事をしている。自分の家と同じような行事を行う。毎月行事を行っており、行事を通じて、皆いきいきとしている。
- 音楽療法。行事を通じて、アドレナリンとドーパミンの働きが活発になる。
- お誕生日会
- 家のように滞在するために、ファミリーキッチンを設置し、愛犬と過ごすこともできる。
- 食事は旬を大事にしている。
- ボランティアの活動はティーサービスやシアターなど多岐にわたり、中には僧侶の方も登録されている。
- 当初からブリーフケアを重視しており、遺族の方へのケアも大事にしている。「しのぶ会」をひらき、家族と思い出を語り、共有する会をしている。
毎年200万人の方が癌で亡くなっていますが、将来的には二人に一人が癌でなくなるだろうといわれています。癌で亡くなる方の死へのプロセスは6段階といわれています。まず、①否認、です。告知された患者はまず自分が死ぬという事実を否定します。そして②怒り。「なぜ、私が今死ななければならないのか」という怒りを覚えます。そして③取り引き、つまり怒りが収まると、患者はもう少し生き続けたいと願い、医師・運命・神などに対し、死を少しでも先へ延ばしてくれるよう交渉を試みます。そして④抑鬱です。いよいよ近いうちにすべてを失わなければならないという自覚が深いうつ状態を引き起こす。最近は様々な薬がでていますが、しかしどうしても我慢できない時もありますので、抑鬱がでます。そして、⑤受容。死が避けられないという事実を素直に受け入れようとする態度になります。そして、⑥期待と希望、つまり死後の生命を信じる患者の場合は、永遠性への期待と希望という段階に入り、平安のうちに死を迎えられます。
ホスピスで最後の時を迎えられた中に、手記を残してくださる方もおられます。ここでは、了解を得られている方の手記と写真を紹介します。
山田さんの「ホスピスの時間の流れで得たこと」を紹介します。「私は自分の人生に満足している。家族に恵まれ、友達の恵まれ、仕事や趣味にも恵まれ、心の底よりこの世に生を受けたことに感謝している。この気持ちを失いたくない。長命ではなくても、己の人生に納得した人間の顔であの世に旅立ちたい。私は強い人間ではない。聖人君子でもない。普通の欲を持った、弱さをもった人間だ。死に至る苦痛が恐ろしい。不安だ。私は、「軟異抄」という書物に出合ったことで人生が変わった。「親鸞聖人」という人物に出会ったことで人生が変わった。煩脳まみれの私が救われている不思議さにありがたくて涙が出ることがある。私の人生は、42.195kmのフルマラソンではなかったが、(30km位かな?)私にとっては十分な長さだった。 私は、薬師山ホスピスのスタッフに感謝している。この様に心やさしい人達を、この様に団体で接したことは始めてだ」。
人間は、意味を繋いでいく動物です。繋がっていることを意識し、そこで安らぐことができます。
「時の出逢い・流れの中で」
日常で「死」について実感することはなかなか難しい状況ですが、薬師山の患者と家族が教えてくださることは最後まで、「その人らしく」「生きている」という現実です。それを、患者と家族、スタッフが一緒になって実感できる事です。そんな地道な取り組みを続ける。その連続がホスピスではないかと感じています。
患者の生きていた事実は、スタッフの心の中に残るだけでなく、次の患者のケアへ活かすことで、患者が生きた「証」が残ります。また、医療者同士が「生」と「死」について話す機会へとつながることができます。
「看取りとは・・・各自の役割」
看取りとは、「命に関わる、最後の時期を共に過ごすこと」であり、そして「専門性を、お互いが生かし、患者を理解する」、「患者の心に寄り添い、見守り、共に生きる」、「主人公は、「誰」なのかを見失わない」、「死に逝く人・残される人の意味を考える機会」であり、そして「新たな出会いに感謝し、忘れない。(失うものと、得るものがあるということ)」、「与えるのではなく、与えられている」ことを知ること、そして「最後に出逢う者として、その人にとってふさわしくありたい」と感じています。
「薬師山で大切にしていること」
薬師山で大切にしていることは、まず「丁寧なケア」、そして「さりげなく謙虚に、をこころがける」こと、「丁寧に今を大切に関わる事が出来ることに感謝する」、「患者さん、ご家族が苦痛に感じていることを緩和する」、「痛い処置を減らす」ことです。そして「一緒にいる時の空間や雰囲気を意識する」「一分一秒が大切な時間ということを念頭におく」、「日々の何気ない会話をする時間(生活や天気など)」、さらに「スタッフ同士のコミュニケーション」「スタッフもひとりの人間として自分の感情や気持ちに素直になる」ことです。
「グリーフ・ケアについて」
国立がんセンターの片桐先生は奥さんを亡くされたとき、奥さんの希望でそれをすぐには公表されなかったのですが、手記によると「亡くなった後の3ヶ月は人間崩壊だった」と書かれています。1年経過して、ようよう日常を取り戻しつつある、という状態であったそうです。
亡くなる方だけではなく、残された人の意味を考え、どうサポートするかということも考えなければいけません。グリーフ・ケアが重要なのです。それには、悲嘆教育、悲嘆プログラムの重要性とともに医療的、宗教的、社会的支援が必要で、診療報酬による支援が必要だと考えています。先日、芸能リポーターの梨本さんが肺癌でなくなりましたが、奥さんの手記には「6ヶ月間は非常に時間密度が高かった」と残されています。亡くなられた直後は神経が高ぶっていますが、それ以降はケアが必要です。そしてそれはボランティアではなく、報酬として資金的に、法制化を含めて展開しないと長続きしません。一方、欧米ではこれについてトータルのネットワークができています。
「自分らしく幸福に死ぬために必要なこと」
このためには、生き方同様、死に方も自分で決められることが大事です。余命の告知を受け、延命治療を望むのかそうでないのかを自分で決め、そして病院か、在宅か。在宅の場合は、1人のケアをするに当たり最低3名は必要です。しかし現状の日本では、難しい状況です。
■意見交換
長谷川
それでは、講演を受けて、質疑をいただきながら意見交換を行いたいと思います。医者ができることとできないこと、宗教者がそこにどう関わっていくかについてのご意見もお寄せください。
大井先生は「痴呆老人が何を見ているか」という本の中で、認知症の認定は国や環境によって異なるが、人のつながりの中で生きていく患者は認知症と診断されにくいと書かれています。
西村周三氏 (京都大学副学長) ※肩書きは研究会開催時のもの
今回の研究会は、以前からずっとやりたいと考えていました。今日はこのように沢山の方に参加いただいて開催できたこと、とても嬉しく感じています。
先生に質問をさせていただきたいのですが、入門編の質問ではなく、中級編の質問です。
まず田辺先生にお伺いしたいのですが、私は小さい頃は知恩院と南禅寺の間くらいに住んでいましたが、幼少の頃から度々早朝講義を聴きに行っていました。そしてかなり小さい頃に座禅もしました。人よりも宗教にご縁があると感じていますが、そこで感じているのは、「みんなと一緒に拝む」のと、「一人で祈る」意味の違いを考えています。
これは、家族の将来とも関係します。最近は「孤独死」「無縁社会」などといわれていますが、京都に住んでいると小さい頃から正月は神社に参り、彼岸やお盆はお寺にお参りし、月参りも行い、クリスマスもイベントをする、という暮らしの中で、皆が一緒にお参りする機会があります。しかし今はそのような機会も随分と減っています。信仰心が減少しているのもありますが、一緒にお祈りする機会が減っているということも重要だと思うのです。そして社会が「死ぬということ」について考える機会が減っているように思います。
ホスピスは、死期を迎えている人が一緒に何かを共有しているのでしょうか。そしてそれは宗教を通して共有することは可能なのでしょうか。「最後は一人」とはいいますが、ホスピスで「最後は一緒に」ということはあり得るのでしょうか。
私は自信を持っていいますが、死は怖くありません。しかし、誰かと一緒に、というのは悪くないと思います。
そこで質問ですが、私は終末に向けた準備をいつから始めたらいいのでしょうか。お坊さんに尋ねると「今すぐ」といいますが、そのようなことは無理です。鎌倉時代などは「明日死ぬかもしれない」という毎日でした。そしてその頃の仏教は、良いことを色々してきましたし、良い言葉も多数残しています。しかし、この社会はなかなか死ねません。一方、癌は割と正確に死期を予測できます。そして終末に向けた計画も立てやすいと思うのです。私は64歳ですが、堀場さんの年齢になったら準備を始めたらいいのでしょうか。「明日から準備だ」といわれることもありますが、一人でするより、他の人との関わりの中で生きているわけですから、その中で自分のことだけに専念するのはいつからしたらいいのでしょう。
例えば、ホスピスに癌ではない方はおられるのでしょうか。おられるのでしたらどのような暮らし、準備をされているのでしょうか。
大井先生の痛みの指標化に関する研究によると、必ずしも強くたたいた方が痛い、というのではないということを知りました。そのあたりの話についても聞かせてください。
大井氏
痛みについてつっこんで調べたことはありませんが、東京都立松沢病院の記録でいえるのは、認知症の人は癌の強い疼痛を感じていないことです。麻薬の使用が認知症の癌患者ではほとんどありません。また終末期医療では、何処まで延命努力をするか、例えば胃ろうを設置するといったことが問題となります。認知症については、自分で意志決定ができません。嚥下困難、つまりものをのみこめなくなることでチューブで食事をするのが良いのかどうか、なるべく早い段階で考えを聞いています。私は、ものが食べられなくなって亡くなるのが一番自然な死に方だと考えています。即身仏というのがありますが、これは五穀を絶って念仏を唱えながら亡くなることですが、食べ物を食べなくなって亡くなるのが一番楽なようです。終末期医療で一番気を使うのは、苦痛があるかどうかです。身体的苦痛に対してはモルヒネがありますが、精神的な苦痛については、宗教界が考えるべきことだと思いますが、「実体的自我」に目覚めると死が怖くなります。60数年前までは皆にかこまれて自宅で亡くなるのが普通でしたが、今は80パーセントが病院死です。孤立した環境で「なぜ世の中で俺だけが死ななければいけないのだ」と思うようになります。
田辺氏
終末をいつから意識したらいいかという質問についてですが、江戸時代は「人生50年」だった訳なので、50歳に入ったら準備をしていったと思います。段々と欠けていくのが50歳代です。それまでもポツポツと欠けていくのですが、60代になると欠けるのがスピードアップします。意識としては、50歳を過ぎたらいつ終末が訪れてもいいように準備をしておくのが良いと思います。
ホスピスでは、エイズ患者も扱います。ただ、日本ではエイズ患者を扱っているのは1箇所だけです。大半のホスピスは癌患者のみです。医療側から患者一人一人に対してのコミュニケーションはやっていますが、患者相互のコミュニケーションは難しいです。コミュニケーションが困難になってからホスピスに来られることが多いので、患者同士のコミュニケーションは少ないです。
人が繋がる感覚、例えば一緒に拝むのは安心感があります。一方一人で拝む行為は不安を伴う行為です。認知症は随伴症状、つまり暴言を吐いたりする等の行為がなければ、「なったもの勝ち」と医者としても思っています。
沖縄県の渡嘉敷村と東京都の認知症の比較が70年代にされています。これによると、随伴症状が伴う認知症の方は東京の方がかなり高く、渡嘉敷村の高齢者はとてもかわいらしいということです。人間が幸せに生きることに繋がるものとして、祈りというのは大きいと思います。
横江桃国氏 (養徳院住職)

西村先生はとても挑戦的な言い方をされていましたが、質問された内容はあまりに入門編であったと思います。生死の問題は年齢に関係ありません。誰もがいつ死ぬか分かりません。20歳代には20歳代の生死感があって良いですし、生まれた以上は必ず死にます。道元は「生死一如」「生死即涅槃」と言っていますが、その通りのことです。生きることも死ぬことも哲学的思考を本来は持っていたはずですが、この30年間はこれが欠落してきていると感じます。50歳から準備するのではなく、妻帯すれば嫁と子どものことを考え、自分の生き様を考えなければいけません。
この研究会では、ぜひいろんな意見を戦わす中で、良い形に花を咲かしていければ、と思っています。私のところでは「不良少年を見てくれ」「ノイローゼーの方を見て欲しい」という要求がありましたので、そのような青年を多く見てきましたが、宗教者として、終末期医療にどう関わっていくかということも大事だと考えます。私たちがどのような接点を持って行くかという議論になっていくように期待しています。ぜひ坊主にはきつい質問をぶつけて欲しいですし、私もそのような意見を出したいと思います。ぜひ議論を戦わせる場にして欲しいです。
堀場雅夫氏 (堀場製作所最高顧問)

平均寿命というものがありますし、数字が正しいと信じるのであれば、確率が高いところで死ぬ、と予測して準備をしたらいいのではないのですか。一人で亡くなるのが嫌であれば、是非一緒に殉死する人を探して、色々と関係を作って、一人か二人を見つけておけば、安心できます。生きている間にそのような人を見つけると、安心です。しかし、おそらくは一緒に死んでくれないでしょうが。
私は53歳の時に本業を譲り、70歳になると「自分ができることは全てやった。いつ死んでもいい」と思いました。しかし80歳になったとき、「あまりにも何も分かっていない」と気づき、その現実に愕然としました。戦中私は学生でしたので、西洋哲学を学んでいません。そこで、岩波の全書を読み始めましたが、なかなか進みません。目が悪くなっていることもありますし、私は最初にざっと読んで、大事なところは何度も読み、さらにそれを自分で書き写しますので、時間がかかるのです。あと5,6年ないと読み切れません。ようは、今まだ死にたくないのです。
人生の終わりの時のみ、お坊さんが出てきます。死に際だけ出てきても、メインディッシュを食べずにデザートだけ食べるようなもの。ぜひ、宗教心を持たせる社会にマッチして欲しいと思っています。
私の両親はキリスト教で、子どもの頃から日曜学校に通いました。しかし30歳の頃に、私は牧師を破門しました。その牧師は共産党かぶれで「労働者から搾取している」と、私に言い始めたのです。その牧師だけの問題かもしれませんが、そのような人を在籍させているという事実もありますので、私はその時にキリスト教と縁を切りました。
教会はレベルが低くても、日本語で説教しています。しかし、坊さんはお経をあげていても、何を言っているかさっぱり分かりません。手短にして欲しくてお金を出しても、さらに長くなる、という有様です。イタリアオペラも何を言っているか分かりませんが、舞台横にテロップを出していますから、舞台を理解することができます。例えばお経にテロップを入れてはどうですか。もう少し日常との距離を短くして、死に際だけではなく、小さいときから宗教心を持てるようにして欲しいと思います。
京都は宗教の町ですし、京都がやり始めれば、他の都市も続くと思います。
中野東禅氏 (曹洞宗総合研究センター講師)

大井先生のお話を久しぶりに伺いました。今回、この会の相談を受けたとき、京都から情報を発信していこうと、そして医療で日本人的な文化、生き方を考えていこう、という点は賛同しました。しかし、会の名前が気になります。15年ほど前からこのような取組はありますし、そこでホスピスが生まれてきました。今回新たに検討を始めるにあたり、ネーミングは新たに考えた方が良いのではないでしょうか。
医療は、とても幅広いです。過剰医療もあります。生殖医療については過剰要求の側面もあろうと思います。要求と生命の限界の矛盾、対立があります。このような行為に対しての提言もできるのでしょうか。
現象論を繰り返すだけでは、生産性はありません。心の奉公によって事態が変わることも期待できるのでは。過剰医療に対してのあきらめの問いに、我々宗教が関わることができるのではないでしょうか。
「知足」つまり「足るを知る」ということが大事です。努力は大事なことですが、その問題については知足が大事です。例えばアメリカでは、体外受精については、4回までやって駄目であれば止める、となっています。こういった情報を咀嚼して、発信することはされていません。そこが、私たちには期待されているのではないでしょうか。
アジアの宇宙観は、混沌の中から生まれます。一方欧米は神が生み出すものです。私たちは他の自然物と同じという価値観があります。これを医療の現場にうまく発信すれば、ものすごいインパクトを持つと思います。岡田真理子さんが、医学系の大学で動物霊を奉っているところの調査をしていますが、これは大正期に始まり、韓国でもあるということです。これが、アジアの宇宙観です。罪滅ぼしの儀礼、キリスト教のパンとワインも疑似儀礼です。水子供養しかり、なぜ死ぬことに夢中になるか、生きることにはそうではないのか、等の整理も必要です。仏教界ではこれまで、脳死など死ぬことに対しては行動を起こしていますが、しかし生まれることに対しては無頓着でした。これまでとは異なる発信の仕方を考えないと、議論はまとまりませんし、実際これまで30年近く議論を重ねてきています。
長谷川
せっかくこの議論を京都でするわけですから、焦点を絞って取り組んでいきたいと思います。ネーミングについても、この会の趣旨を明確にして決めていくべきものと考えております。
横江氏
一人で祈るというのは、修行的な行為です。一方、多人数で祈るのは信仰の行為。親が拝めば、子も拝みます。その後ろ姿に美しさがあります。禅宗の葬式は最初に七言絶句を唱え、そのあとは漢文をつくります。伝統的なものを引用するだけではなく、個人の略歴を唱えます。それを聞いて、大変喜んでいただける家族もおられます。そのようなお話しは、もっと坊主に指摘していただかないといけません。厳しいご指摘を受けて、宗門も改めることができます。
西村氏
経済の話になりますが、「足るを知る」については、資本主義の今まではそのような価値観ではなく、欲望を追求する社会です。そしてそれは自己決定権と繋がります。欧米人は小さい頃から自分で決める、という教育をされています。日本人は違うような形で自己決定をするような所もあります。例えば、みんなで喫茶店に行って、本当はコーヒーが飲みたいのに、みんながコーヒーを注文するから「私は紅茶」というようなもの。みんなと違うことを言ったりするのがそうだと誤解している点もあります。
「私の命はもう十分です」といいたいのですが、それには勇気が要ります。その時に宗教者のアドバイスが欲しいのです。
大井氏
みすず書房から出版した「環境世界と自己の系譜」で論じていますが、自己観が日本人とアメリカ人では異なります。それはなぜでしょう。簡単に言うと、日本人は狭い国土に沢山の人と平和に生きなければいけませんから、自分だけではなく他の人の意向も尊重しなければいけません。それを無意識のレベルで行っているのを文化心理学者たちが見出しています。19世紀半ばペリーが来航してきた時、アメリカの30分の1(そのうち平野部は約2割)の面積の日本では3千万人が国土に暮らしていました。一方アメリカには広い国土に2千万人。先住民を殺し、黒人を奴隷として使役していた。攻撃的に暮らしていかないと生存できなかった。
今後は完全な閉鎖系である地球の資源が枯渇していく中、日本のような閉鎖社会の生き様が参考になると思います。江戸時代の生き方は、現代の私たちも参考になります。迷惑をかけずに生き、死んでいく。
一神教の社会では「自分の神が偉い」となり、ヤーヴェでもアラーでも、それぞれが偉いと主張します。しかし多神教の所は、文明の衝突は言われていません。統治も穏やかです。つながりをもっと大切にする、という考えを大事にしていくことが必要でしょう。
田中滋氏 (龍谷大学教授)

私は50歳代ですが、西村先生のような幼少体験はなく、宗教心はあまりありません。私は神戸で育ちましたので、幼い頃から寺に通うようなチャンスもありませんでした。田辺先生にご質問ですが、「死へのプロセス」について、若い人も同じようなプロセスを辿るのでしょうか。消費社会において、若い人がどのような発想でそのように至るのでしょうか。
アメリカ映画では、一人の人が何人も殺戮を繰り返すというのはよくありますが、日本映画にはそのようなものがありません。日本は精神と肉体が分離できないという発想があると思います。ですから、日本のものづくりにおいても、ものに精神的なもの、アミニスティックなものを抱きます。人間の肉体を道具として使う、そして悪くなれば「取り替えて」というのは起こりにくいと思いますし、心身二元論はホスピス、終末医療においてどのようなものなのでしょうか。
田辺氏
統計としてとっているわけではありませんので、経験的なものですが、プロセスについてはスキップする方もおられますし、一つの段階の時間がかかる人もいます。若い人の方が、時間がかかるように感じています。
ものに魂を入れる感覚は、日本人の心の中にあると思います。ホスピスはシシリー・ソンダースが言い始めたことですが、徐々に広がり始め、選択肢の一つとして確立しています。日本風のホスピスは患者の希望に応じてカソリックでも仏教でも可能です。患者の心の安らぎが期待と希望に繋がります。ものが食べられなくなった際には胃ろうを作りません。食べなくなり、枯木のように亡くなるというのが苦痛が少ない、と思っています。
大井氏
胃ろうについては、私も反対の立場を取っています。口からものが入らなくなったときに、命が終わったと考えるのが良いと思います。世界には多くの飢えている人がいる中、これから死ぬ人に対してじゃんじゃん栄養を入れることを疑問に思いますし、胃ろうを施しても長期間生きながらえるわけでもありません。逆流して誤嚥性肺炎を起こす危険もあります。
デカルト的な心身二元論ではなく、私は一元論を信じています。一度も、魂と肉体は別だという現象を見ていません。人間の生きている状態については、「命が私をしている」「命があなたをしている」が正確ではないか、と思っています。亡くなることで宇宙に還るのです。年をとると色々と辛いこともありますが、宇宙に還ることでスッとそれが無くなるのは魅力的なことだと思います。
長谷川
京都の持つ宗教的な財産を活かし、宗教、哲学を考える都市・京都を目指したいと思います。今回のテーマの医療と宗教ですが、何を採用して何を整理するかの取捨選択については、次回の研究会でもおおいに意見を交わしていただきたいと思います。そして、来年2月には公開シンポジウムを開催し、この活動の輪を広げるきっかけをつくりたいと考えております。

宮城泰年氏 (京都仏教会常務理事 聖護院門跡門主)
坊さん、イコール死、というイメージがあるかもしれません。しかし私どもは「死」ではなく「生きる」ことを大事にしています。私の宗派では、乞われれば葬式もしますが檀家はいません。死はどう生きるか、ということと関わってきます。この問題はずいぶんと以前から考えている命題でもありますし、これからも続くでしょう。私は、この会にもっと坊さんが参加して欲しいと思っています。